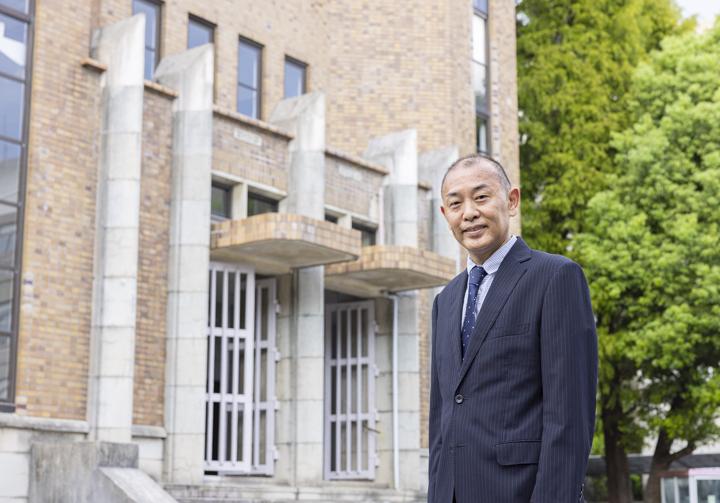仕事のプロ
2017.09.27
「一見非情にみえる優しさ」で向き合う
女性IT起業家ヒストリー2:起業と子育て

80年代に群馬県で女性SEとして起業し、現在ソフトウェアやシステムの開発のほか、ネットワークやセキュリティー設計・構築までを手がける株式会社OPENERで代表取締役会長を務める六本木佳代子さんへのロングインタビュー。4人の子どもを育てながら30年以上第一線で働き続けてきた彼女の半生を「仕事と“天職”」「子育てとの両立」「リーダー論」「ワーキングマザーへのメッセージ」というテーマに分けて4回シリーズでお届け。 第2回は、まだまだ男性の育児参加が一般的でなかった時代に会社を辞め、起業し、4人のお子さんの育児に奮闘した時代を振り返っていただいた。
- 家事や子育ては1人で
抱え込まずにメリハリをつける - 六本木さんが結婚し、2男2女の子育てに奮闘したのは1980年代から1990年代にかけての時代。当時は、数年間会社勤めをしたら専業主婦になる女性がほとんどだった。しかし六本木さんは、「子育てと仕事をどうやって両立させていこうか」とは考えても、子育てに専念するために仕事を辞めようという発想はまったくなかったという。その理由は、「仕事は人生そのものだから」
とはいえ、4人のお子さんを育てるだけでも並大抵のことではない、と想像はつく。長女の誕生は1984年。次女が1986年。双子の長男と次男が1993年。お子さんたちが小さかった頃は、職場結婚したご主人が会社を辞めて家業を継いだばかりということもあって外出が多く、家事や育児の協力は望めなかった。時代的にも男性の育児参画はほとんどないのが一般的で、4人の子育ては六本木さんひとりが背負うことになった。
さらにその頃、六本木さんは第一子の出産明けからフリーランスのSEとして活躍し、1986年、旧会社法により、株式会社化には1000万円の資本金制限があった時代に有限会社ジー・エム・ケー(1988年に株式会社に改組)を設立した。仕事が加速度的に忙しくなっていくタイミングと、子育て真っ盛りの時期が重なったわけだ。六本木さんは、それまでは一人で何もかもやろうとする傾向が強かったそうだが、試行錯誤する中で「一人でできることはたかが知れている」と気づいた。仕事もプライベートも、他人と協力することで、自分の思いを何倍にも拡げることができると気づいたのだ。
「すべてを自分でやろうとするのはやめて、頼れるところは周りに頼ることにしました。義父が孫の面倒をよくみてくれたので保育園のお迎えなどはお願いし、夜に取引先で作業をしなければならないときは実家の母に預けました。家事代行サービスではないのですが、近所の方に報酬をお支払いして掃除や洗濯などをしていただいたこともあります。その代わり、食事をつくったり、忙しくてもこどもたちと食卓を囲んだりする時間は大事にしました。他の人にお願いしてもいいことと、自分が大切に思う譲れないものを区別したら、気持ちがラクになりました」 
- 一時の感情に流されず
こどもの成長を見据える - ただし、「こどもと一緒にいてあげたい気持ち」がどれほど強くても、仕事に向き合わなければならない時がある。特に、ジー・エム・ケー設立後しばらくは自宅の一角や同じ敷地内が会社だったため、こどもたちがそばにいる環境で仕事をしなければならなかった。こどもが寂しがって泣いている声が、ドア一枚隔てた職場にいても聞こえてくることがあった。
「このドアを開けて、ちょっとでも抱っこしてあげられたら...。何度そう思ったかわかりません。でも、扉を開けることはしませんでした。今、私が自宅に顔を見せたら、あの子は『泣けばママが来てくれる』と思うようになってしまう。うちは両親が働く家庭なんだから、この環境を受け入れられる芯の強い子に育てることこそ必要なんだ、って」
母を恋しがって泣いていた次女は大人になってから、「木製のドアが、"鉄でできた扉"にみえた」と笑いながら語ったそうだ。それでも、こども心に「ママにはお仕事があるんだ」と理解し、気丈に泣きやんだ。後に六本木さんは、稲盛和夫氏が主宰する経営者のための私塾「盛和塾」で「本当の優しさは、一見非情にもみえるもの」という言葉を教わった。まさにその言葉を実践するのが、六本木さんの子育てだったのかもしれない。
「一時の感情に流されない」とは、「一時の感情で衝動的な行動をとらない」ということでもある。この子育て哲学が活きたのは、長女の中学時代だった。ご主人の仕事の関係で一家がシンガポールに移住したばかりの時期で、英語が話せないのにいきなりイギリス系のインターナショナルスクールに放り込まれた長女は、ある日学校をさぼってしまったのだ。
「先生から『お嬢さんが来ていない』と電話があったときはびっくりしたけれど、長女の行動範囲には危ない場所もなかったので、どっしり構えることにしました。先生には、『具合が悪くて寝ています。連絡をし忘れてすみません』とウソをつきました(笑)。帰宅しても自分から問いつめることはしないと決めていましたね。言葉があまり通じなくてつらい思いをしているのはわかったので、毎日登校しているだけで花マルだ、と思っていましたから。ここで冷静に接すれば、長女はまた前を向いて歩き出せるはずだ、と感じたんです」
うしろめたそうに帰宅した長女は、ほどなく「実は今日ちょっと...」とすべてを打ち明けた。六本木さんはまず、「先生にはウソついちゃった!」と笑って話した。そして、「ママも英語が苦手で、みんなの言っていることがわからなくてイヤになることがあるよ。でもママも頑張るから、一緒に頑張ろうね」と自分の弱点をさらけ出し、「1年ぐらい学校に行かなくても、長い人生ではたいしたことじゃないよ」と励ました。
「追いつめずに逃げ道をつくってあげた方が、こどもはかえって頑張ろうという気持ちになれるかな、と思って」
この事件で長女との絆はより深まったそうだ。
- 瞬間ごとの真剣さは
こどもに必ず伝わる - そんな六本木さんに「子育てで一番辛かったことは?」と聞いてみた。「小さい頃一緒にいてあげられなかったこと」...そんな答えをなんとなく予測して。しかし返ってきたのは、「次女の結婚式に出席できなかったことですね」という言葉だった。結婚式が行われたのはバリ島。ちょうどその頃、グループ会社のトラブルに巻き込まれ、その渦中にいた六本木さんは日本を離れるわけにはいかなかったのだ。
断腸の思いで次女に欠席の旨を伝えると、「私はずっと経営者の娘だから、ママの責任感の強さはちゃんとわかってるよ。経営者としての仕事を全うしてね」と笑顔で逆に励ましてくれた。六本木さんは、「悲しい思いをさせるのだから、私は自分の責務を精一杯果たそう」と考えた。式当日は、「バリには行けなくても、自分にできることをしよう」と、Skypeを通して参加した。
その1年後、六本木さんはこどもたちから思いがけないプレゼントを受け取ることになる。台湾のリゾート地に家族が集まった際のことだ「記念の家族写真を撮るから、ちょっときれいな服を着てきてね」と言われ、少しドレスアップして集合場所へ行くと、ウェディングドレス姿の次女とタキシードを着た義理の息子が待っていた。長女も長男も次男も結婚式とまったく同じ服装で笑顔を浮かべている。六本木さんのために、1年前の式当日と同じ写真が撮れるようセッティングしてくれていたのだ。
「もう、涙があふれてしまって。私は決して、100点満点の母親ではなかったと思います。でも、仕事と同じように子育ても、一瞬一瞬を真剣に取り組んできました。こどもたちはみんな、口には出さなくてもその姿を見ていてくれたんだな、と温かい気持ちがわき上がりました」
その次女に息子が生まれ、六本木さんはおばあちゃんになった。次女がFacebookに書き込んだコメントを見ていたら、「自分が母になって改めて、母の無償の愛をかみしめる」といったフレーズが。無償の愛をきちんと受け取ってくれた娘の言葉に、六本木さんは涙が止まらなかったという。 
- 第3回は、起業から現在までの波瀾万丈な経営者人生をお聞きしながら、女性リーダーに必要な考え方や行動について探っていく。

六本木佳代子
群馬県生まれ。情報処理工学を学び、卒業後はSEとして勤務。退社後はフリーランスとして活躍後、株式会社ジー・エム・ケー、株式会社ジーニアスエンタープライジング、株式会社OPENERを設立。現在はOPENERの代表取締役会長。盛和塾にて稲盛和夫氏に学んだ人間学の知識や、10年以上にわたるシンガポール居住経験を生かし、枠にとらわれない経営を実践する。著書に、自社社員への「今日の言葉メール」をまとめた『ハート・オブ・マム――無償の愛が人を育む』がある。
文/横堀夏代 撮影/ヤマグチイッキ