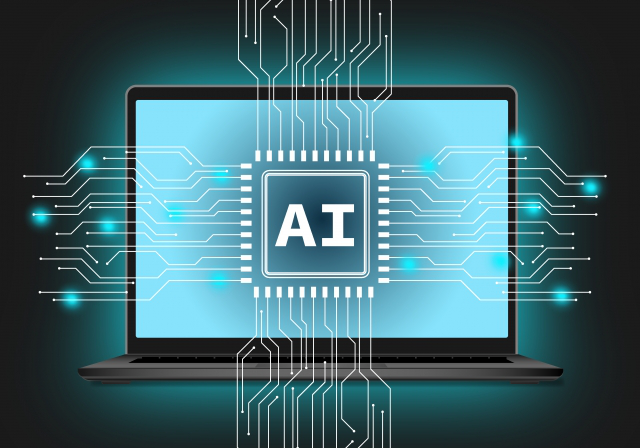トレンドワード
真にサステナブルか、企業の姿勢が問われるSDGsウォッシュとは?
トレンドワード:SDGsウォッシュ

持続可能な社会の実現が国際社会共通の目標として掲げられ、共有認識が広がっていく一方で、意図的に、あるいは意図せず、表面上と実際のSDGsの取り組みに乖離がある「SDGsウォッシュ」が問題となっている。その内容やリスク、国際的な規制の動向や回避方法について解説する。
SDGsウォッシュとは
SDGsウォッシュとは、一見すると社会や環境に良いことをしているように見えて、実際は中身が伴っていない取り組みや発信を指します。「環境に良い」と掲げる活動に対して、実際はビジネスのことしか考えていない取り組みに対する「グリーンウォッシュ」という批判が語源と言われています。 グリーンウォッシュが環境対応に特化した見せかけの取り組みに対する批判なのに対して、SDGsウォッシュはそれに加えてジェンダー、労働、教育、人権、平和などSDGsの17目標すべての取り組みへのごまかしなどが対象となります。
SDGsウォッシュの事例
具体的な事例として、企業の次のような行動がSDGsウォッシュとして批判されました。
SDGsウォッシュが企業に与えるリスク
SDGsウォッシュが企業に与えるリスクには、まず企業イメージの低下や信用失墜が挙げられます。実際に海外のNGO団体から日本企業が「強制労働をさせているサプライチェーンから製品を輸入している」と指摘され、バッシングを受けたケースがあります。こうした指摘が不買運動につながったり、採用ブランドが棄損されて人気がなくなる、融資が受けられなくなるなどの可能性も考えられます。 さらに、環境保護団体や消費者によるグリーンウォッシュやSDGsウォッシュに対する訴訟も世界的に増加傾向にあります。国によって規制やルールに違いがあるため、海外展開している企業には落とし穴になる場合もあるようです。
SDGsウォッシュが起こる背景
こうしたSDGsウォッシュが起こる背景として、SDGsに対する知識不足や認識の甘さ、部門間やサプライチェーンとのコミュニケーション不足などが挙げられます。 また、SDGsは努力目標であってノルマや義務、罰則はないため、仮にごまかしやSDGsに逆行する行動が行われていても、取り締まることはできません。そのため見過ごされてしまったり、優先順位を下げられるケースも考えられます。 また、真面目にSDGsに取り組もうとすると、材料費や輸送コストが上がるなど経済合理性に合わないことも、理念と事業での取り組みに乖離ができる原因となっています。
SDGsウォッシュに対する各国の規制強化の動き
欧米諸国ではSDGsウォッシュやグリーンウォッシュに対する規制の強化が急速に進んでいます。 例えば欧州(EU)では「グリーン・クレーム指令」を公表。これは消費者がグリーン移行に積極的に貢献できるよう、環境に関する虚偽の表現を規制するためのものです。具体的には、「環境に優しい」「エコロジカル」「グリーン」「生分解性」といった、あいまいな表現を使うことが禁止され、商品の環境性能をPRする際には科学的根拠の提示や、第三者機関による定期的な検証結果の開示が求められます。 また、耐久性に関する虚偽の訴求や、必要以上に早い段階での消耗品の交換を促す表示なども禁止されています。 イギリスでは2021年に「グリーン・クレーム・コード」を制定。「真実かつ正確であること」「明瞭であること」などの6つのガイドラインに基づき、広告基準協議会(ASA)がAIを使って企業の表現をモニタリングし、問題のある広告がないか監視を行っています。ASAによる広告規制の適用例として、環境への配慮の誇張や誤解を招くマーケティング表現を使ったとして、大手航空会社に宣伝活動の禁止と巨額の罰金が科されたケースなどがあります。 さらに韓国でも、環境配慮に関する虚偽や誇張表現を用いた企業に罰金を科す法案が発表されました。 日本では明確なSDGsウォッシュに対するガイドラインや規制は定められていませんが、事実と異なる表示が行われている場合、景品表示法違反となる可能性があります。具体的には、生分解性を有するような表示をしたプラスチック製品が、実際は根拠のないものだったとして、景品表示法違反を消費者に周知徹底するなどの措置命令が日本企業10社に出された事例があります。
SDGsウォッシュを避けるために企業が取るべきアクション
SDGsウォッシュを避けるために取り組むべきこととして、まずはSDGsに関する正しい知識を身につけることが挙げられます。SDGsの本来の意義に立ち戻って企業活動を見つめ直し、社会的責任をどう事業に落とし込むか、方針を決めて社員に情報共有することが大切です。そのためには専門部署の設置や、重要課題の特定と明確なKPIの設定、サプライチェーン全体の把握と管理、社内研修の実施などの取り組みが求められます。 また、SDGsへの取り組みを謳う場合、裏付けとなる根拠や評価が必要となります。マーケティング上のインパクトや効果だけにとらわれて、安易にあいまいな表現や誇張した表現を使うのは避けなければなりません。そのためにも、表示内容が適切かチェックリストを作成したり、第三者から検証を受けるプロセスを設けておくと安心です。さらに透明性を担保するためには、サステナビリティレポートを定期的に発表するなど、社外に向けて報告を行うとよいでしょう。 SDGsは2030年までの達成目標に対し、2024年時点で進捗は16%と大きく後れを取っています。コロナ禍による経済の停滞や地政学的な影響などさまざまな要因が考えられますが、このままではSDGsが表面的な謳い文句となってしまい、持続可能な社会の実現が難しくなります。 SDGsウォッシュに対する風当たりの強さは、逆にいえば企業としての社会的責任を果たすことが正当に評価される環境になってきているともいえます。 企業の社会に向き合う姿勢が企業価値を上げる一方で、違反が見つかれば罰則を受けたり、取引ができなくなるリスクがあります。経済合理性と環境配慮や人権配慮を融合させるための試行錯誤を繰り返していく姿勢がますます求められています。