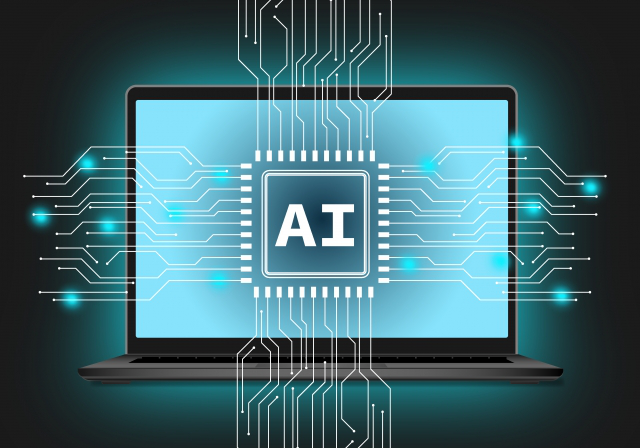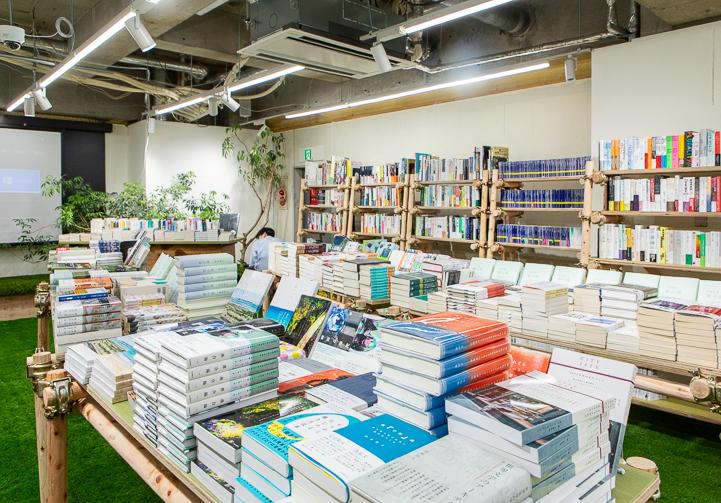トレンドワード
職場の「なんで伝わらない?」の正体─増え続ける"コミュニケーションコスト"とは
トレンドワード:コミュニケーションコスト

「職場の課題の8割はコミュニケーション」といわれるほど、社内のスムーズなコミュニケーションが必要不可欠。コミュニケーションにかかる余計な時間や手間を放置すると、業務効率の低下だけでなく、組織全体の生産性や心理的安全性にも影響を及ぼしかねない。本記事では、コミュニケーションコストの正体とデメリット、改善策を解説していく。
「コミュニケーションコスト」とは
コミュニケーションコストとは、商談や業務連絡、何気ない社内の会話などにおいて、情報伝達や意思疎通を行う際に要する時間や労力のこと。ここでいうコストには、時間だけでなく、情報の伝達や収集、意思決定や調整にかかる労力やエネルギーなども含まれます。 コミュニケーションを取ることは重要ですが、時間や労力がかかりすぎたり、うまくコミュニケーションが取れず業務に差し障るといったコミュニケーションコストが高い状態は望ましくありません。 コミュニケーションコストが高い状態の具体例として、「何度も同じことを伝えなければならない」「報告や相談先がわからない」「メールやチャットを開いてもらえない」「言ったことが正確に伝わらない」「情報更新が関係者に認知されない」「伝達ミスで手戻りが頻繁に発生する」などが挙げられます。 また、相手に何か伝える際に「気を遣う」「遠慮してしまう」「不安を感じる」といった感情的・精神的なコストも、コミュニケーションコストといえます。
コミュニケーションコストが意識されるようになった背景
近年コミュニケーションコストが多くの企業で注目されるようになっている背景には、ハイブリッドワークの定着によってコミュニケーションの形が変化したことがあります。 また、社会的に生産性や心理的安全性に対する意識が高まっていることや、若手とベテランで情報伝達に使うツールや頻度が異なるなど、世代間でコミュニケーションに関する意識のギャップも挙げられます。 さらに、DXを進める中で、ツール導入は進んでもコミュニケーションの質やルールの整備が追いつかず、結果としてコストが増大してしまうといった影響があると考えられます。
コミュニケーションコストが高くなる原因
伝達ミスによる手戻りや意思疎通のすれ違い、チャットを見てもらえないなど、コミュニケーションに余計な時間や手間がかかる原因として、以下のような要因が考えられます。
時間的余裕がない
業務が多忙すぎてコミュニケーションに割く時間がないため滞るケースは多いです。特に管理職には連日報告や相談、決裁の依頼など重要な連絡が大量に寄せられ、会議などで時間を拘束されることも多く、捌ききれないという悩みを抱えるリーダーも多いようです。
発信される情報の量やツールが多すぎて埋もれる
明確なルールもないまま、メールやチャット、社内SNSなど様々なツールを多用したり、関係者を過剰に増やしたりすると、優先順位が高い発信も埋もれてしまい、気づかれないことも。また、発信や情報更新の頻度が高すぎて、見るべきタイミングがわからず、放置されるケースもあります。
前提となる目的やゴールが正しく共有されていない
「何のためにこれを伝えているのか」という目的やゴールが共有されていないと、人によって解釈が異なったり、誤解が生じたりします。その結果、なかなか理解されず何度も質問を繰り返すなど、無駄なやり取りも増えがち。伝える側にも受け取る側にもストレスがたまる状況です。
コミュニケーションを取りやすい雰囲気がない
伝わりづらいと感じる背景に、心理的安全性の低さが潜んでいる場合もあります。上司や先輩に質問しづらい、会議で意見を言いづらいなど、伝える心理的ハードルが高いと感じさせる雰囲気がある場合、なかなか円滑なコミュニケーションは生まれません。
コミュニケーションコストが高い組織の問題点
コミュニケーションコストが高い組織には多くのデメリットが生じます。具体的な影響として、3つのポイントがあります。
業務効率が低下
不要な会議や過度なメールのやりとりなどに時間を取られてしまうと、本来時間をかけるべき作業ができません。また、上司や関連部署の確認が取れないために素早い対応ができず、ビジネスの機会を逃してしまうケースも。
チーム間で連携が取れない
必要な情報が適切に共有されていれば、チーム内や部門間で協力し合えたり、新しいアイデアが生まれたりするシーンも多く見られます。コミュニケーションコストが高いためにそうした機会を逸してしまうことは、大きな損失だといえます。
社員が疲弊する
情報が正しく伝わらないことによる誤解や手戻りなどによって、余計な時間を取られたとストレスを感じてしまうことも。また、ひどい場合には「どうせ言ってもムダ」と感じさせるなど、無力感や孤立感、不信感などにつながってしまう場合もあります。
コミュニケーションコストを下げるためにできること
成果につながる情報伝達をするため、コミュニケーションコストを下げる、またはコミュニケーションの質を上げるためにできることとして、次のようなアクションがあります。
コミュニケーションスキルの向上
ちょっとした伝え方の工夫や意識づけで、伝わりやすさは大きく変わります。例えば、コミュニケーションスキルに関する研修やオンボーディングの実施、「結論から伝える」「5W1Hで構成する」などテキストコミュニケーションのひな形をつくるなどが挙げられます。また、専門用語や社内用語の解説をまとめたり、ルールやマニュアルを作成することも効果的です。
コミュニケーションを取りやすい環境づくり
気軽に話しやすく、会議などでも安心して発言できる環境をつくることも重要です。例えば横断プロジェクトなど部門を超えたコミュニケーションの機会を設ける、会議での発言ルールを決めるなど、オープンな組織づくりに向けた取り組みが求められます。また、オフィスのレイアウトや動線もコミュニケーションへの影響が大きいといわれています。
リーダー層の意識づけ
会議やメールなどのやり取りはリーダーの意向や価値観が大きく表れます。リーダー自ら、会議に時間をかけない、回数を増やしすぎない、率先して効率的なコミュニケーションに取り組むなどの姿勢を見せることが効果的です。
適切な人員数の配置
「遅れているソフトウェアプロジェクトへの要員追加はプロジェクトの完了をさらに遅らせる」というブルックスの法則に見られるように、人員が増えると調整すべき情報量やコミュニケーションパスが増えがちです。「チームの人員数はコミュニケーションコストの観点で見て適切か」も意識したチーム構成が求められます。
社内ツールの見直し・ルールの明確化
コミュニケーションや情報共有のツールが乱立していると、見落としが発生しやすくなります。コミュニケーションの目的や種類に合わせてツールを使い分ける必要があります。その際、部門ごとのローカルルールは極力つくらず、統一されたルールに添って活用されるのが望ましいでしょう。
まとめ
コミュニケーションコストは、日々の業務の中で"見えにくいけれど確実に存在する損失"です。コストを最小化する工夫は、単なる効率化ではなく、心理的安全性や組織の創造性を高める土台にもなります。一見コストに見える対話や雑談も、実は信頼や補完関係を育む機会になっている場合も。コミュニケーションコストの見直しは会社全体で取り組むべき課題であり、その解決にかける時間は有益な「投資」といえるでしょう。