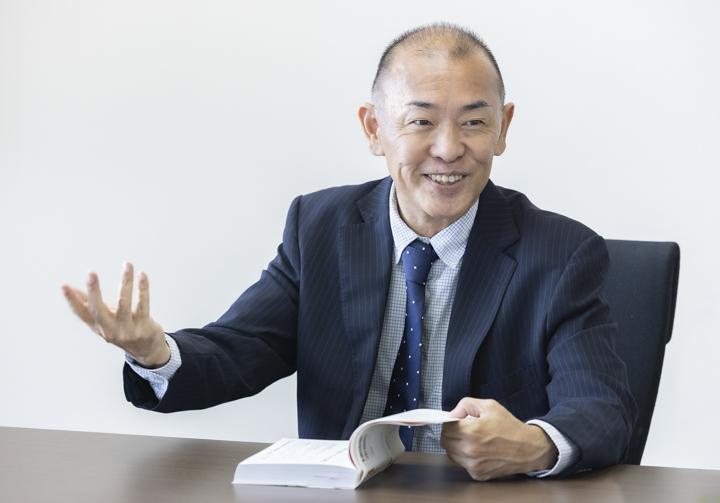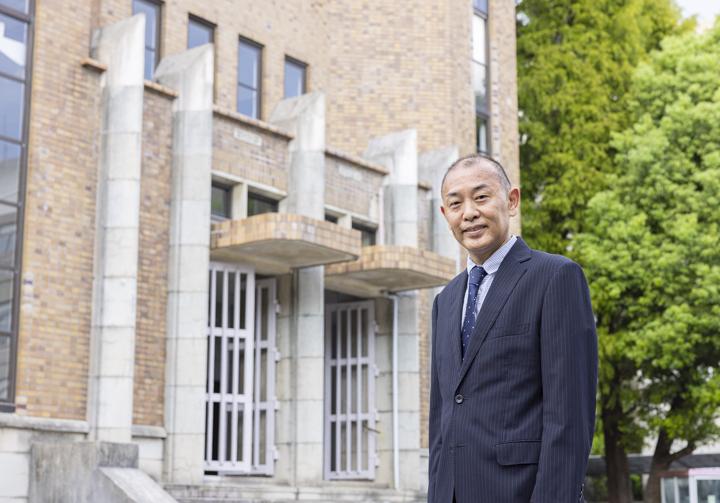仕事のプロ
「脱・失われた30年」の仕事と学びを考える〈前編〉
目的思考・コスパ思考ではイノベーションは生まれない

社会が急速に変化するなか、経営者であれワーカーであれ「学び続けること」が必須の時代になっている。一方、会社や上司の要請に応じた業務に必要な範囲の学びで良いのか、学びが自己や会社の成長に本当につながっているのかと、疑問を感じるワーカーもいるのではないだろうか。何をどう学ぶかよりも、その根底にある「学習観・仕事観」に目を向けるべきだと言う法政大学経営学部経営学科の長岡健教授に、これからの学びと仕事について伺った。
国際競争力を取り戻すには、仕事観・学習観を 変えるラディカルな意識変容が不可欠
―まずは、長岡先生の研究テーマや研究室の活動についてお聞かせください。
越境学習や大人の学びを中心に、「学習観」、つまり「学びをどう理解するか」について、それが「仕事観」や仕事のパフォーマンスなどとどのような関連があるのか、相互に作用しながらいかに変わっていくのか、動的な視点で研究をしてきました。
例えば、「知識や技能を得ることが学習である」と考えていた人が、「他者との対話により新しい視点を得ることが学習である」と考えるようになったとします。その変化を単体で分析するのではなく、学習観の変化に伴い、仕事の意味づけや仕事への取り組み方、キャリアや家族、人生に対する考え方がどのように変わったかを紐解くというのが、私の今の研究のスタンスです。仕事観が変わることで学習観が変わるという逆の流れもあり、学習観と仕事観は相互に絡み合うものだと捉えています。
また、長岡研究室では「創造的なコラボレーションのデザイン」をテーマに活動し、サードプレイス(第三の場所)となる対話の場づくりなどに取り組んでいます。学生には慣れ親しんだコミュニティを飛び出す越境体験を課しており、noteやポッドキャストなどでの日々の発信に加えて、年に4回、誰でも参加できる「カフェゼミ 」という実験的なオープン・ゼミも開いています。

―長岡先生が「学習観」や「仕事観」を研究するうえで、課題意識はどこにあるのでしょうか?
ひと言で言うと、いわゆる「失われた30年」です。今の若い世代には信じがたいことかもしれませんが、日本の国際競争力は、1989年から1992年は世界1位でした。そこから30年かけて落ちていき、2024年には38位まで転落しました。
学生には「もしサッカーのFIFAランキングで世界1位だった国が38位まで落ちたとしたら、国内リーグが一体どんな状況になるかを想像してほしい」という話をします。国内リーグだけを視野において、その中で勝ち残ればいいという発想では、みんなで一緒に落ちていくだけ。それで本当に大丈夫なの?いや、大丈夫じゃないよね...と。

 もはや日本の遅れは、知識やスキルを手軽に身につければなんとかなるというレベルではありません。このままだと、間違いなく「失われた50年」になってしまいます。30年間右肩下がりに落ちてきた状況を変えるには、これまでのやり方を根本から変えて新しいことにチャレンジしなければなりません。そのためには、仕事や学びに対するマインド(=仕事観・学習観)を変える、ラディカルな意識変容が不可欠なのです。
もはや日本の遅れは、知識やスキルを手軽に身につければなんとかなるというレベルではありません。このままだと、間違いなく「失われた50年」になってしまいます。30年間右肩下がりに落ちてきた状況を変えるには、これまでのやり方を根本から変えて新しいことにチャレンジしなければなりません。そのためには、仕事や学びに対するマインド(=仕事観・学習観)を変える、ラディカルな意識変容が不可欠なのです。
コスパ思考、勝ち抜き思考では、 パフォーマンスも価値も上がらない時代に
―国際競争力が低下した要因はどこにあるとお考えでしょうか?
大きな要因の一つに、ビジネスをはじめ物事をコストパフォーマンスの観点で捉えてきたことがあります。若い人たちの間にも広がる「コスパ」ですね。コストパフォーマンスとは費用対効果であり、成果に対するコストをいかに下げるかが肝になります。つまり、出すべき成果というゴールを定めたうえで追求するものであり、想定以上のパフォーマンスは上がりません。
コスパを優先した結果、30年間でここまですり減ってきたのが日本の経済です。そして、こうした状況では、言うまでもなくクリエイティビティは発揮されず、イノベーションは起こりません。
また、「競争を勝ち抜く」から「みんなの幸せ」へと、グローバル社会の価値観が大きく変わったのも重要な点です。幸せとは、いわゆる「ウェルビーイング」です。学生には「ウェルビーイング=経済的な価値と非経済的な価値を合わせた幸福度の指標」と説明しています。実際、国際競争力ランキングの上位には、デンマークやスウェーデンといったウェルビーイングを重視してきた北欧の国や、シンガポール、香港、台湾といった新しい考え方をもつ国がランクインしています。競争を勝ち抜くだけの古い資本主義的な発想を超えて、ウェルビーイングなどの新しい視点を含めて、仕事や学びについて見直す時期に来ているのです。

―しかしながら、企業やワーカーにはそこまで危機感がないように感じます。
危機感がないから、これまで何もしてこなかったから、イノベーションが起きなかったから、その結果として38位という現状があるのです。なぜ実感や危機感が生まれにくいかというと、個人の経済実感にはストックが影響するから。日本経済には過去のストックがあり、GDPもある程度高い数字を維持してきましたが、近年はじわじわと下がっていますよね。これからはどんどん他国に抜かれます。 しかしながら、企業の方にこうした話をしても、50〜60代は「逃げ切れる」と思っているし、中堅層は組織にがんじがらめ...というケースが多いのが実情です。 一方、学生に「君たちが40代になる頃は...」という話をすると、「そんな状況は嫌だ」と言います。未来ある学生たちには、「このままではダメだ」という危機感をもち、「何をやってもどうせ変わらない」という諦めではなく「これまでの当たり前を本気で変えていこう」という思いをもって社会に出てほしいと願っています。
業務上のスキルアップが目的ではない、 「自分がやりたいからやる」学びを
―では、組織に属するワーカーは、自らの学習観や仕事観をどう変えていけば良いのでしょうか?
一つに、仕事を時間で区切らないことが挙げられるでしょう。例えば、「業務時間内か業務時間外か」という見方は、仕事を時間で捉えているからこそ起こる発想です。「業務とは別に取り組んだこと・学んだこと(=越境学習)が仕事につながった」というのはあくまでも結果論であり、日頃から越境学習を実践できている人は、「業務時間内か外かは後から決まるもの」と思っているはずです。 時間報酬型か成果報酬型かというのは企業のビジネスモデルや人事・労務の仕組みに大きく左右されますが、ワーカー一人ひとりが「どれだけ働いたか(時間)」ではなく「何を生み出したか(成果)」というマインドにシフトすることが大事です。 また、学習においては、目的指向からの脱却も大切です。業務上のスキルを高めることを目的にした学びではない、「自分がやりたいからやる」「何にどう役立つかわからないけど、やってみる、飛び込んでみる」ような主体性のある学びに変わっていくと、新しい価値創出にもつながるでしょう。今やっていることの意味は後から決まる。だから、やる前から結果を気にし過ぎずに、プロセスを真剣に楽しむ姿勢が大事。日頃から学生にもそう伝えています。
―「主体性のある学び」というのは、どういうことでしょうか?
会社や上司の意図や希望とは無関係に、ワーカーが自らの意志で取り組む学びのことです。「主体性」に似た言葉に「自主性」がありますが、元・麹町中学校校長で教育者の工藤勇一氏は著書の中で、「自主性と主体性を履き違えてはいけない」と指摘しています。工藤氏曰く、自主性とは教員がやってほしいことを生徒が先回りしてやることであり、主体性とは教員の思惑とは異なることも含めて生徒が自らの意志でやることであると。
ビジネスでも同じで、「上司が部下に願っていることを、部下が自発的にやる」という状況は主体性のあるアクションではありません。大事なのは、誰に何か言われたわけではないけど「やりたいからやる」、「学びたいから学ぶ」、ということ。つまり、内発的動機に基づいた学習です。
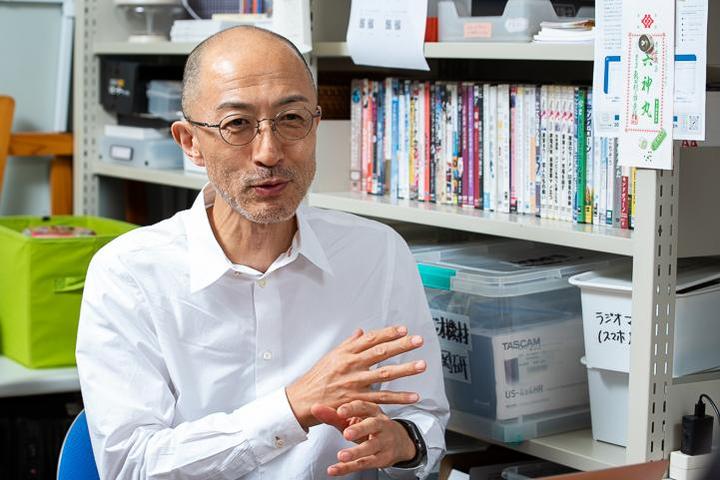
湧き出る内発的動機がなければ イノベーションは起こせない
―内発的動機に基づいた活動・学習が結果として仕事につながる...という状況を考えると、ワーク(仕事)とライフ(プライベート)がシンクロするようなあり方になるのでしょうか?
そうですね。イノベーションの創出においては、ワークかライフかといった線引きはないというのが本来のあり方です。言い換えると、心から湧き出る内発的動機に基づきやりたいことをやる人にしか、イノベーションは起こせません。やらされてやる仕事には、到達できるレベルに限界があるのです。 もちろん、すべての内発的動機がビジネスに通じるわけではありません。例えば、ゲームが心から好きであっても、それが仕事につながるケースは稀でしょう。仕事につながる内発的動機の要素には、自立心、知的好奇心、探究心に加えて「利他性」があります。つまり、誰かのために、何かの役に立ちたいという利他的な意識と内発的動機が結びつくことで高い成果が生まれるのです。 一方、実際にイノベーションを起こせる人材は100人に1人という世界ですし、起こせる確率が低いからこそ価値があるのがイノベーションです。すべてのワーカーにイノベーションが起こせるわけでも、それを求められているわけでもないというのもまた事実です。しかし、自分には関係ないと切り捨てたり、小手先のTIPSのようなものに頼ったりするのではなく、一人ひとりが根本から仕事や学びについて考え直す姿勢をもち、それが多くの人々に浸透している社会にイノベーションが起きるのだと思います。 後編では、新しい学習観や仕事観にシフトし、価値創造に挑戦するために企業や個人ができることについて、引き続き長岡先生に解説していただく。
【関連記事】「脱・失われた30年」の仕事と学びを考える〈後編〉
長岡 健(Nagaoka Takeru)
法政大学経営学部教授。東京都生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、イギリス・ランカスター大学大学院・博士課程修了(Ph.D)。組織論、社会論、コミュニケーション論、学習論の視点から、多様なステークホールダーが織りなす関係の諸相を読み解き、創造的な活動としての「学習」を再構成していく研究活動に取り組んでいる。越境、アンラーニング、サードプレイス、ワークショップ、エスノグラフィーといった概念を手掛かりに、「創造的なコラボレーション」の新たな意味と可能性を探るプロジェクトを展開中。著書に『みんなのアンラーニング論』、『ダイアローグ 対話する組織』(共著)、『越境する対話と学び』(共著)など。