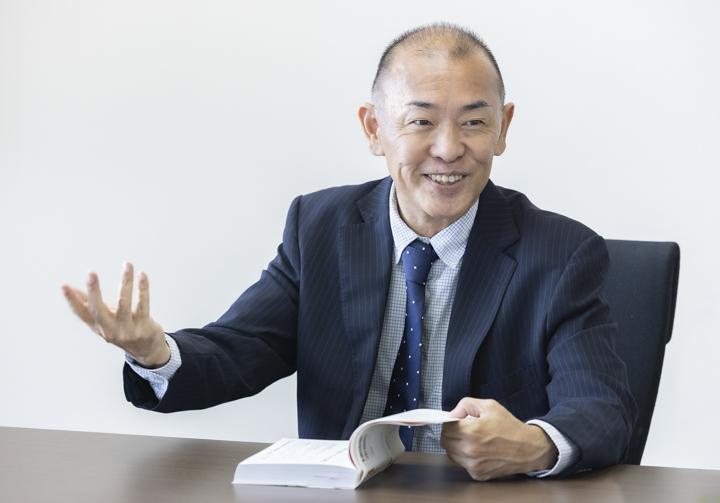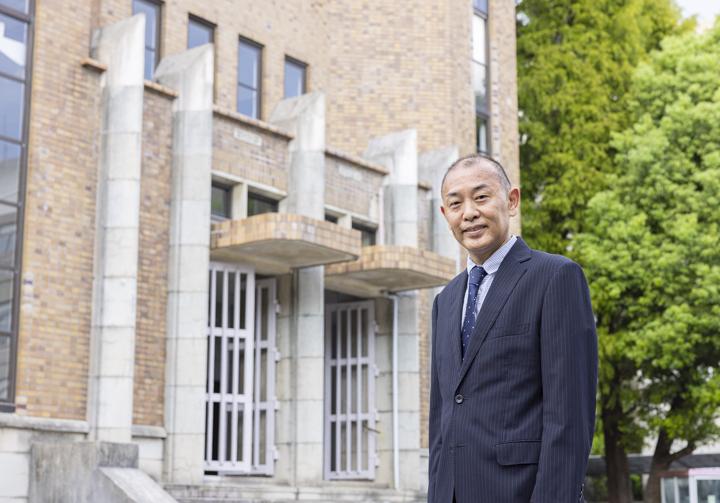仕事のプロ
「脱・失われた30年」の仕事と学びを考える〈後編〉
同調圧力のない自由な発想が生まれる場をつくるには?

「失われた30年」を経て、2025年の国際競争力ランキングでは35位という結果になった日本。企業やワーカーの学習観・仕事観からラディカルに変革し、これまでのやり方を変えてイノベーションを起こすしか道はないと、法政大学経営学部経営学科の長岡健教授は語る。後編では、「内発的動機」をキーワードに、企業や個人がすべきことについて、引き続き長岡先生に解説していただく。
内発的動機をもとにアクションを起こしている ワーカーに、会社のリソースやエネルギーを割く
―実際の日本の組織において、内発的動機に基づいて自ら動いているワーカーは多くはないと思います。企業はそうした人材が育つ土壌をいかに育めば良いのでしょうか?
イノベーターの資質のあるワーカー、つまり、強い内発的動機をもとにアクションを起こしているワーカーに、リソースやエネルギーを割くことです。 昨今のモチベーション研究は、圧倒的に内発的動機付けが主流ですが、かつては外発的動機付けが盛んに研究されてきました。これはいわば、サボらせないための研究です。しかし、外発的動機を与えていかに頑張らせたところで、そこからイノベーションは生まれません。 一方、誰かに言われなくてもいい仕事をするワーカーや、試験と関係ない内容でもしっかり勉強する学生はいるものです。放っておくとサボる人を外発的動機付けによりサボらせないようにするのか、自分でどんどんやりたいことに挑戦する人を後押しして育てていくのか。経営戦略的にどちらに投資すべきかは明白でしょう。
―組織経営論的には、新しい学習観や仕事観をどう組み込み、イノベーションにつなげていくべきでしょうか?
従来のヒエラルキー型の組織を崩し、プロジェクトベースでフラットな組織を構成することが大事だと思います。ここで言うプロジェクトとは、特定のミッションを与えられた少人数からなる期間限定型チームのこと。プロジェクトごとに活動することで、「やりたい」という強い内発的動機をもつイノベーティブなメンバーを中心に、エネルギーの高い状態で短期集中型の業務に取り組むことができます。 ここで大事なのが、プロジェクトのリーダーに権限委譲すること、そして、ヒエラルキーを持ち込まないことです。うまく行っている会社では、グループ会社としてプロジェクトチームを立ち上げ、やりたいと手を挙げた社員を社長にすることですべての権限を渡している例もあります。プロジェクトベースの組織は、若手の育成にも向いています。
自由な発想をイノベーションにつなげるには、 同調圧力をなくし対話を行うことが不可欠
―組織におけるイノベーションを阻害する要素としては、どのようなものがあるのでしょうか?
イノベーティブで自由な発想を阻害するもっとも大きな要因は、集団凝縮性や同調圧力です。それをいかに組織からなくすかが、イノベーションを起こせるかどうかを大きく左右します。仲が良いメンバー、意見が合う同質性の高いメンバーを集めて話し合ったところで、多様なアイデアは出てきません。
決定権をもつ集団が仲良しメンバーで構成されている組織は非常に危険ですが、現実としてそうした例は少なくありません。こうして生み出される同調圧力が、日本の変革をダメにしているのです。
また、自由な発想をイノベーションにつなげるためには、自分とは異なる意見や価値観をもつ人、初めて会った人とも対等に意見を交わす「対話」が不可欠です。対話は、意見を交わし合って賛成・反対を明確にする「議論」とは違うし、近しい人同士の「会話」とも異なります。日本人は対話に不慣れですが、考え方の異なる人と話をするうえでは、対話のスキルが非常に重要になります。

―対話のスキルとは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
まずは、相手の話に耳を傾けることです。相手の意見には賛成も反対もせず、共感します。共感と同情は異なります。相手の意見が自分にとって受け入れ難いものでも、ひとまず「そうなんだ」と受け止めることが共感です。 また、議論の場では「意見を変えたら負け」という空気があり、自分の意見を変えたり取り下げたりするのは容易ではありません。一方、対話には勝ち負けはなく、むしろ、いろいろな人の意見を聞いたうえで自分の意見を変えるのはいいことだとされ、参加者同士で意見を変えやすい雰囲気をつくりだそうとします。アイデアの可能性を広げるための組織内の話し合いで求められるのは、まさにこの意味での対話なのです。
―組織におけるイノベーションを阻害する要素としては、他にどのようなものがあるのでしょうか?
従業員エンゲージメントの低さも課題です。自分のためなら頑張りたいけど、チームのためには頑張りたくない、というワーカーが多いんですね。「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」というアフリカの諺がありますが、別に遠くに行きたくないしみんなでも行きたくない...というわけです。所属する組織やチームへのエンゲージメントをいかに上げるかは内発的動機にも大きく関わることであり、組織にとっては取り組むべき重要課題であると言えるでしょう。
パラレルキャリアと越境学習の実践で、 自分らしい働き方と広い視野が得られる
―新しい仕事観として、今後はワーカーの働き方も変わってくるとお考えでしょうか?
はい。学生には、パラレルキャリアやフリーランス、副業・複業といった働き方やキャリアを念頭においてもいいのでないかという伝え方をしています。実際、そういう働き方をしている人は増えていますし、今後も増えるでしょう。 ゼミの卒業生でも、大手企業に正社員として勤めながら自分がやりたい領域でNPO法人を立ち上げ、軌道に乗ったところで企業を退職してNPOの活動に絞った、というケースもあります。つまり、内発的動機に基づいて、やりたいことをやる、という働き方です。 大学卒業後すぐに起業したりフリーランスとして活動したりするのはハードルが高いので、そういう学生にはまずは複数の職業をもつパラレルキャリアからスタートすることを推奨しています。 一方、労働者派遣法などの影響もあり、こうした働き方が主流になるにはまだ時間がかかりそうです。法制度も含めて、ナレッジワーカーのための複業・副業の整備が必要だと考えています。
―組織に所属して肩身の狭さや不自由さを感じているワーカーに向けて、アドバイスをいただけますでしょうか。
リンダ・グラットンは著書『ワーク・シフト 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図』の中で、友人として「親友」「同志」「ビッグアイディア・クラウド」の3タイプをもつことを推奨しています。親友は精神的な安らぎをもたらす仲間、同志はプロジェクトを共に進める仲間、そしてビッグアイディア・クラウドは世界を広げてくれる仲間です。自分とは異なる興味や視点をもつ人々(=ビッグアイディア・クラウド)との交流を通じて、関心領域や視野を広げることができると同時に、閉ざされた世界から飛び出す勇気が湧いてきます。その結果、自分にとって当たり前の考え方やモノの見方を見つめ直し、自分の進むべき方向や目指したい未来像を探索できると、彼女は述べています。
これはまさに、「越境学習」の考え方です。たとえ組織に所属しているとしても、常に越境マインドをもち、内発的動機に基づいて自分らしく自由に生きている人たちのネットワークとつながることで、組織内の集団凝縮性や同調圧力から抜け出そうとするポジティブな気持ちが湧いてきます。そんな人たちに出会うために、コワーキングなどのサードプレイスに足を運んでみるのも良いでしょうし、週末にボランティアやインターンシップに参加するというのも良いでしょう。そうした場や機会は増えているので、ぜひ一歩踏み出してみてほしいと思います。

求められるのは、チームで創造的活動に 打ち込める、組織本体から切り離された場
―新しい学習観・仕事観のもと、多様な人々の対話が生まれ、イノベーションが起きる。オフィスをそうした場にするためには、何が求められるとお考えでしょうか?
イノベーションラボ的な場が肝になると思います。そもそも、同じ時間・同じ場所にメンバーが集うというのは、「コスパ」で言うと悪いですよね。コストはかかるけど、それだけプライスレスな時間・空間なんだという重要性を集まるメンバーが理解すること、そのうえで、集中してクリエイティブな活動にみんなで打ち込むことが重要です。 2005年頃に生まれたのが、「グループ・ジーニアス」という考えです。これは、グループであるが故に生まれてくる天才的発想や創造性のことを意味し、これを発揮するためには「グループ・フロー」と呼ばれる一種のゾーン状態に入ることが重要であるとされています。グループ・フローに入るには、「自立的であると同時に、協力的であるメンバー」「管理されていないのに、一丸となれるチーム」「リスクのある状況でも、積極的な挑戦ができるチーム」といったパラドクスを受け入れ、脱・二元論的な思考・行動を実践することが求められます。このグループ・フロー状態が生まれやすいオフィスの実現は、イノベーションと空間デザインに関する重要なテーマとなるのではないでしょうか。 そして、こうしたイノベーションラボ的な拠点は、本社ビルなど組織の本体から物理的に距離のある場所に作るのが良いように思います。これまでにない新しいこと、ちょっと変わったことに取り組んでいる新規事業部隊は、ともすると組織内では冷たい目で見られがちです。同調圧力に屈しないためにも、あえて本体からは離して隠れ家的な存在にすることで、自由な発想でイノベーションが生まれるのではないかと思います。
【関連記事】「脱・失われた30年」の仕事と学びを考える〈前編〉
長岡 健(Nagaoka Takeru)
法政大学経営学部教授。東京都生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、イギリス・ランカスター大学大学院・博士課程修了(Ph.D)。組織論、社会論、コミュニケーション論、学習論の視点から、多様なステークホールダーが織りなす関係の諸相を読み解き、創造的な活動としての「学習」を再構成していく研究活動に取り組んでいる。越境、アンラーニング、サードプレイス、ワークショップ、エスノグラフィーといった概念を手掛かりに、「創造的なコラボレーション」の新たな意味と可能性を探るプロジェクトを展開中。著書に『みんなのアンラーニング論』、『ダイアローグ 対話する組織』(共著)、『越境する対話と学び』(共著)など。