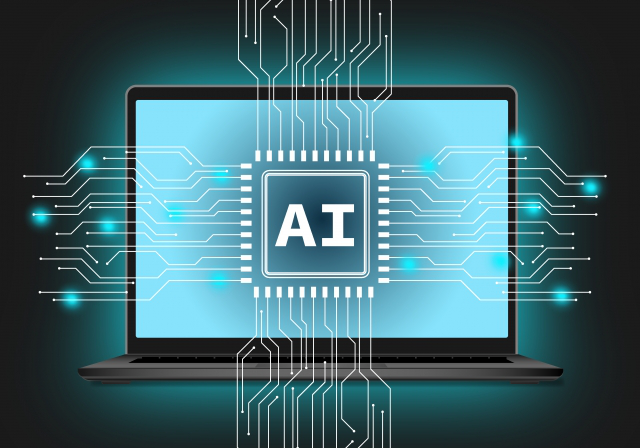トレンドワード
AI時代にこそますます重要になる、感情労働とは
トレンドワード:感情労働

メンタルヘルス不調による休職や離職の増加が深刻な課題とされるなか、特にそのリスクが大きいとされる、感情労働。AIが多くの仕事を代替すると言われているが、人間にしかできないことも多い感情労働の重要性はますます高まっている。感情労働の特性や対象となる職種、バーンアウトを防ぐために企業や個人が取るべき対策について解説する。
肉体労働、頭脳労働に続く第三の労働形態「感情労働」とは
感情労働とは、相手(顧客や患者など、業務上の他者)の感情に配慮し、自身の感情をコントロールすることで期待されるサービスの質を維持・向上させる労働のこと。身体を使って報酬を得る「肉体労働」、頭脳を使って報酬を得る「頭脳労働」に対して、「感情労働」の従事者は感情をコントロールすることで報酬を得る、第三の労働形態を指します。 生身の人間を相手にし、感情の抑制や緊張、忍耐などが求められるという特徴があります。相手から理不尽に責められたり、攻撃的な言葉を投げつけられたりしても、感情をコントロールしながら冷静に応対したり、相手が納得するまで丁重に説明や謝罪を繰り返すといったことが求められる仕事です。アメリカの社会学者アーリー・ラッセル・ホックシールドが1980年代後半に提唱し、一般的に知られるようになりました。
感情労働の対象となる職種
代表的な感情労働として、コールセンターのオペレーターや苦情処理担当者、金融機関や行政などでの窓口対応部署、客室乗務員や駅員などが挙げられます。他にも、クレームや無理難題に感情を抑制しながら対応や謝罪することが求められる場面の多い看護師・介護士などの医療従事者や接客業・宿泊業のスタッフ、営業担当者なども感情労働だといえるでしょう。 近年ではモンスターペアレントと呼ばれる保護者の対応が求められる教員や、部下をケアする役割を強く求められるマネージャー職なども感情労働化してきているといわれています。
感情労働に見られる特徴
感情労働の特徴として、常にクライアント優位で、かつコールセンターやクレーム対応窓口のように適切な対応をしても感謝されないことが多いため、情緒的消耗が大きいことが挙げられます。また、その精神的な疲労やストレスが外からはわかりづらいことも起因して、負担を感じていることに気づかれず、「燃え尽き症候群」(バーンアウト)につながるリスクが高いとも言われています。 さらに、感情労働では、マニュアル通りの謝罪を繰り返すなど、外面的に期待される感情表出を行う「表層演技」と、例えばクレームに対する謝罪の際に、あたかも心の底から申し訳なさを感じているかのように自身の感情を誘発する「深層演技」をする場面があります。そのため、本音と表出する感情との不一致による葛藤が生じたり、演技している自分に対して「表面的な対応だ」と批判し、感情が疲弊してしまう場合も。 特に共感力や使命感の高い人ほど、感情に寄り添いすぎて疲労してしまう共感疲労が強い傾向が見られます。例えば患者の苦しみを目の当たりにしている医療従事者や、虐待を受けた子どもの話を聞く相談員などが共感疲労に苦しむケースが多くあります。 また、感情を抑制するスキルは、誰もが持っているとみなされる傾向があります。そのため感情をコントロールできないのは、自己の不十分さによるものと認識されがちなことも、感情労働の負担を大きくしている要因の一つと考えられます。
感情労働の現場で取るべき対策
感情労働従事者の負担を少しでも軽減し、燃え尽き症候群を防ぐために取るべき対策として、企業とワーカー個人それぞれについて見ていきます。
企業が取るべき対策の例
感情労働による負担やストレスは外から見えにくい傾向があるため、企業側から定期的に面談を行うなどで状況を確認し、メンタルヘルス対策や過度な負担を未然に防ぐ働きかけが求められます。具体的には以下のような取り組みが必要です。
- ・ストレスチェックの実施
・個別のストレス耐性の把握
・ストレスマネジメントやコーピング等の研修の実施
・仕事の質・量的な負担の調整
・休暇取得の促進
・相談先の明確化
・顧客対応の線引きの明確化
個人が取るべき対策
感情労働に従事するワーカー自身も、自身の心身を守るための対処法に取り組む必要があります。具体的には次のような方法が考えられます。
- ・ストレス発散の手段と機会を持つ
・オンとオフのメリハリをつけ、オフの時間には感情をリセットする
・同僚や上司と定期的に状況の共有を行い、孤立を防ぐ
・完璧主義を手放し、「こうあるべき」に縛られすぎない
AI時代の感情労働の展望
AI技術の進化により、一部の感情労働についてはAIで代替できるようになることが見込まれています。例えばコールセンターでのチャットボットの導入、ホテルや飲食店での受付、音声認識システムによる案内、スーパーやコンビニなどでの無人レジ化、アプリでの交通機関案内やオンラインチケット販売などはすでに導入が進んでいます。また24時間対応が可能で、一貫性のある対応ができるというメリットもあります。定型的な対応や事務処理はAIが担うことで、作業効率が上がり、ワーカーの負荷を減らすことができるはずです。 一方、人間にしかできない感情労働もあります。例えば介護や医療現場での患者・家族への対応やトラブル時の顧客対応のように、相手の気持ちに寄り添ったふるまいや場の空気を読んだ対応、信頼関係や安心感の構築など、高い共感力やコミュニケーションスキルが求められる対応はAIに代替させることは難しいでしょう。 今後はAIが代替できるものや強みが活かせる作業は任せ、人間は共感力や繊細な情感を最大限に発揮した対応に注力することが重要になると言えそうです。そうした人間とAIとの役割分担のマネジメントも、より必要になると予測されます。 感情労働の現場でのAIとの協働によって、ワーカーの精神的負担の軽減やサービスの品質向上、ワーカーのやりがいにつながることが期待されます。