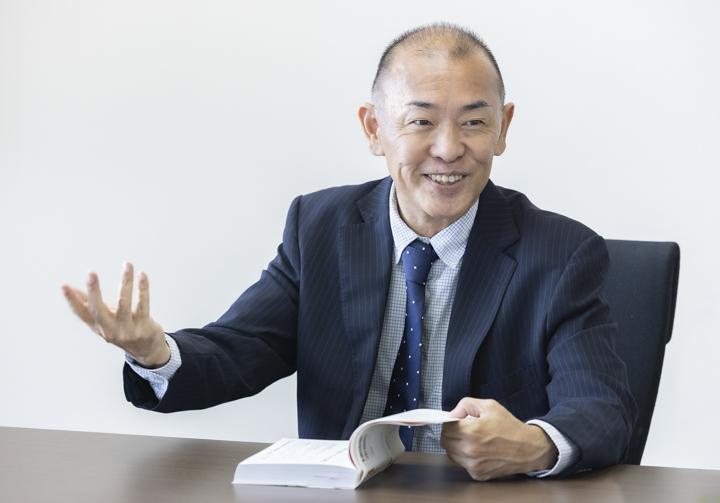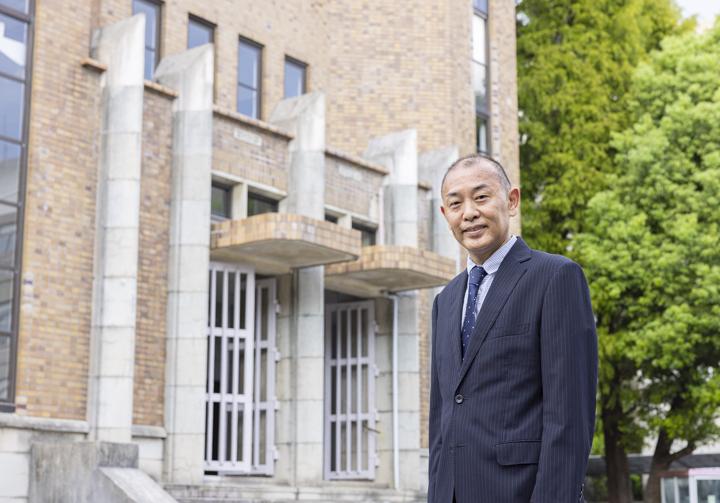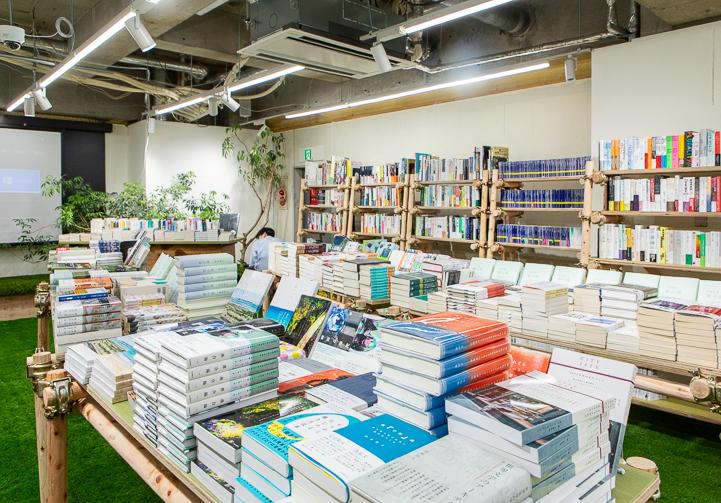トレンドワード
もう"指示待ち"ではない、自ら意思決定して行動する自律型AIとは
トレンドワード:自立型AI
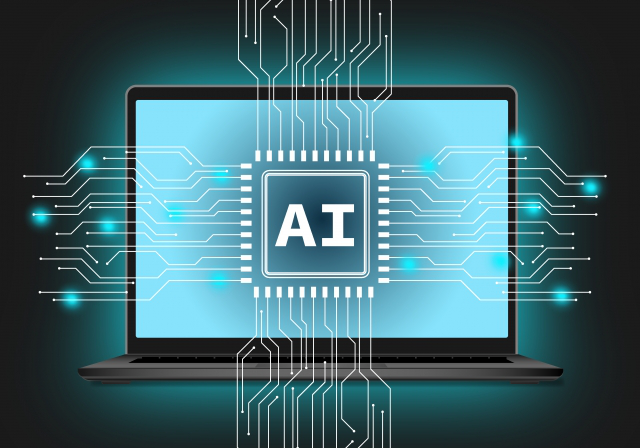
生成AIの登場で飛躍的に業務効率化が進むなど、技術の進化による変化が目覚ましい。さらに従来のAI技術を大きく超え、単なる自動化を超えたパラダイムシフトを起こす可能性を秘めた「自律型AI」の開発が進みつつある。生成AIとの違いやその仕組み、活用事例や注意点などについて解説する。
自律型AIとは
自律型AIとは、特定の業務に特化した作業において、設定された目標に向けて人間の介入なしに自律的に行動し、タスクを実行できるAIシステムのこと。人間による都度の操作や対話を必要とせず、自ら情報収集や判断を行いながら、高度で複雑なタスクを実行することができます。 生成AIとの違いの一つに、AIを使用する目的があります。生成AIは入力されたプロンプト(指示)に従いながら、テキストや画像などの「コンテンツを生成する」という目的で使用されます。一方、自律型AIは、指定されたゴールの達成を目的として、意思決定を繰り返しながらフィードバックを活用し、状況に応じた改善を行えるよう設計されています。ただし、完全な自己学習や自己改善は通常、外部からの設計や監督が必要です。 つまり自律型AIは、「設定されたゴールの達成に向けて、周囲の状況を自ら認識し、目的達成のために最適な行動を自分で考え、実行し、その結果から学習して次に活かす」というPDCAサイクルを回すように設計されているのです。決められたルールに従って作業を繰り返す「自動」ではなく、新しい手順の発見をAI自ら行う「自律」型と呼ばれるのは、そうしたプロセスに由来します。
自律型AIの仕組み
自律型AIはゴールの達成に向けて次のようなプロセスで作業を行います。
- ① 目的・ゴールをもとに、必要なタスクを生成
② タスクの優先順位を決める
③ タスクの実行
④ 結果を評価し、改善タスクを生成
自律型AIのビジネス活用事例
こうした自律型AIのビジネスの現場で実際にどのように活用されているのか、事例を紹介していきます。
金融業界
問い合わせ対応や業務書類作成のほか、住宅ローンの審査業務、市場動向のデータ解析やリスク調査等の調査レポートの作成、不正行為の検出などに自律型AIが活用されています。また、株式市場や仮想通過取引でも、損失抑制と利益最大化を目標として設定した自律型AIによる取引が行われているケースもあります。
製造業・物流業界
工場や倉庫などでの作業プロセス、生産ラインや配送ルートの最適化、在庫管理や品質管理などを自律型AIによって制御することが浸透しつつあります。自律型AIと基幹システムや製造ロボットなどと接続させ、さまざまなデータを収集・分析することで、生産プロセスの最適化を実現できます。
カスタマーサービス
顧客からの問い合わせにチャットボットなどで自動対応を行い、問い合わせ内容を分析して問題解決のための提案を行います。 さらにECサイトやオンデマンドサービスなどで、顧客の購入履歴や閲覧履歴等を分析。さらに感情分析なども加えることで、パーソナライズされたレコメンドを行うことができます。レコメンドに対する顧客の反応を受けて、さらに最適化していくことも可能です。
会議AI
日程調整だけでなく、会議中の会話の内容を理解して、参加者が必要とするデータや資料を発見し、分析した結果をその場で提示してくれる自律型会議エージェントもすでに実現しつつあり、一部で実証が進んでいます。市場規模予測や需要予測など、ビデオ会議中の発言を受けて必要なデータを収集し、グラフ化して示すなど、生産的な意思決定に必要なサポートを行うことが期待されています。
自律型AIを活用するメリット
自律型AIを活用することで得られるメリットとして、まず業務効率化が挙げられます。自動化による時間短縮によって、人間がよりクリエイティブな作業に時間を使えるようになります。 また、その結果、人件費等のコスト削減にもつながります。24時間365日対応や個別最適化、データ活用による精度の向上、意思決定や業務スピードが上がるなど業務の質を上げながら、人の負担を減らすことが可能になるのは、自律型AIを導入する大きなメリットといえます。人間だけでは実現が難しかったイノベーションが起こる可能性を大いに秘めています。
自律型AI活用の注意点
自律型AIを導入する際にはいくつかの課題や注意点があります。例えば導入時のハードウェアやソフトウェア、インフラの整備などのコストやランニングコストがかかります。クラウドベースの小規模導入では比較的低コストで始めることができることもありますが、大規模なシステム構築では数千万円から数億円規模の初期投資が必要となる場合も。 また、ゴールの設定や監視、修正などを行うAIエンジニアやデータサイエンティストなどの専門人材の確保が必要になり、運用にあたっては社内のAIリテラシー向上も必須となります。こうしたコストや人材への投資に見合う成果が上げられそうか、導入前に費用対効果を見極める必要があります。 さらにAIがハルシネーション(誤回答)するリスクは一定の割合で起こるため、人間によるチェックのプロセスは外せません。また、AIが自律的に行動するということは、判断の背景や根拠などがブラックボックス化します。加えて、AIが収集・分析するデータや情報には機密情報や個人情報を含む可能性もあるため、プライバシー保護法規に準拠したデータ管理が不可欠となります。
まとめ
今後はより自律型AIや自律型ロボットなどの普及が進むことが見込まれています。少子高齢化に伴う労働力不足への対応や迅速な意思決定のサポートとして、AIの活用が期待されます。 それに伴って、人間はより創造的な仕事へとシフトしていくことが予測されます。自律型AIは人間の仕事を奪うものではなく、人間がより本質的で創造的な業務に集中するためのパートナーとして協働していくことが求められるでしょう。