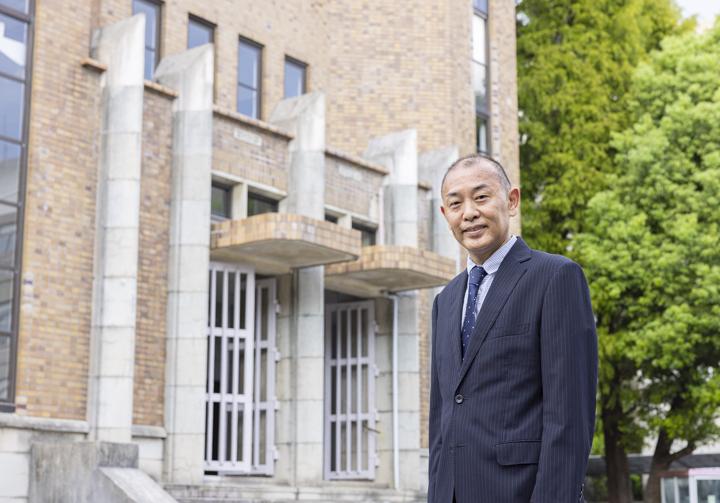仕事のプロ
人類の進化とともに組織のあり方も進化する「ティール組織」とは〈前編〉
ティール組織の3つの特徴と魅力、よくある誤解

次世代型の組織として注目を集めている「ティール組織」。これまでのマネジメント手法と一線を画するまったく新しい価値観であることもあって、表層的な理解に留まることも多いという。そこで日本のティール組織研究の第一人者であり、日本語版「ティール組織」では解説も担当した嘉村賢州(かむら・けんしゅう)氏にその特徴や魅力についてお話を伺った。
ティール組織とは、 進化に合わせて色で表現された5段階の組織モデル
嘉村氏が「ティール組織」という概念に出合ったのは、1年間休業して世界中を回っていたときのこと。Web記事で偶然目にして以来、半年経っても忘れられなかったという。
「人類の進化に合わせて組織がダイナミックに変化してきていることが見事に表現され、さらにその新しい組織モデルを実践している企業の事例が数多く紹介されていて、電撃が走りました」
ティール組織とは2014年にフレデリック・ラルー氏によって紹介された新しい組織モデルであり、「ティール」とは鴨の羽色のような青緑色のこと。組織モデルは人間の意識の発達段階とともに大きく5段階で進化してきており、その進化の段階を色で表現している。5段階の組織モデルは次の通り。
〈組織モデル〉
レッド(衝動型)組織:狼の群れのような力や恐怖による支配で、短期的な思考。マフィアやギャング組織など。
アンバー(順応型)組織:規則、規律による階層構造。長期的展望を持つことが可能に。軍隊、教会、行政機関など。
オレンジ(達成型)組織:階層構造を持ちつつ実力主義も取り入れる。グローバル企業など現在の企業の大半がこれに当たる。
グリーン(多元型)組織:多様性と平等と文化を重視し、ボトムアップで意思決定を行う。NPO法人などが近いと言われる。
ティール(進化型)組織:変化の激しい時代における「生命体型組織」。
「フレデリック・ラルー氏が、世界中から先進的な組織作りを行っている企業の事例を集めて研究したところ、お互いにまったく知らないにもかかわらず、組織運営にいくつかの共通項があることがわかりました。その特徴をまとめたのが『ティール組織』です。教科書となるような理論があったわけではなく、世界中に散らばる先進的な企業がおのおの理想の組織のあり方を模索し、実験を繰り返しながらたどり着いた、ありたい組織の姿がティールだったわけです」

ティール組織に見られる3つの特徴
ティール組織の組織運営の共通項として見られた3つの特徴に、「自主経営」「全体性」「存在目的」が挙げられる。
自主経営
大組織にあっても一人ひとりが決定権を持ち、階層やコンセンサスに頼ることなく仲間との関係性で動くシステム。調達や人事などすべての意思決定はメンバー同士のアドバイスやフィードバックなどの「助言プロセス」に基づいて行う。情報の透明性が重要。
全体性
職場にあっても多様性を認められ、仮面をつけることなくありのままの自分でいられる環境。メンバー同士が自分のありのままの内面をさらけ出しても攻撃されないと感じられる心理的安全性が担保された職場であることが前提となる。
存在目的
組織がこの先どうなりたいのか、何のために進化するのかといった、組織の意思決定を導く原則であり、組織が存在する目的のこと。目的を考え続け、更新していくことで組織はひとつの生命体のように進化を続けていく。
組織への課題意識から ティール組織にのめり込んだ
ティール組織という考え方に出合う以前、嘉村氏は組織のあり方に課題意識を抱き、理想の組織のあり方を考えるターニングポイントが何度かあったという。
一度目は新卒で情報・通信系の会社に入社した時。営業に配属されたが、注意欠陥障害
(ADD)の影響もあって他の人のようにできないことも多かった。
「例えばテレアポや議事録、営業用トークスクリプトの暗記などがうまくできず、つい後回しに。その結果上司を怒らせたり先輩に『人としてどうかと思うよ』とまで言われ、プレッシャーで縮こまるようになってしまいました。
多くの従来型組織では、それぞれの得意なことを任せるのではなくタスクローテーションで様々な経験を積ませ、苦手な業務でもこなせるようにならなければ次に進めないということもよくありますが、私のような特性を持っている人は苦しいでしょう。
私の場合、注意欠陥障害の影響でデコボコがあることを理解してもらえるような関係性がまだ築けておらず、『苦手なことや欠点は克服するものだ』という前提に苦しみました」
一方で大学時代は、国際交流のNGOなど100を越えるプロジェクトの運営に携わり、自分らしさや得意なことを発揮できていたという。
「そこではコミュニケーションに自信を持てていましたし、喜ばれている、役に立てていると感じることができていました。同じ人間なのに組織や環境によって活躍できたり萎縮したりと、発揮できるパフォーマンスがこうも変わるのだと実感した経験でした」
2度目のターニングポイントは、新卒で入社した企業を辞めて立ち上げたNPO法人で、企業での大規模ファシリテーションに取り組み始めた時のこと。人との対話を通して受講者が一度は覚悟を持って意識を変えることができたのに、組織の論理を前にくじけてしまうのを何度も目の当たりにした。
 「個人としては素晴らしいのに、組織構造の中でくじけたり、想いをあきらめてしまう姿を見るうちに、『人類は組織のつくり方を間違えたのではないか』という問いが生まれました。学生時代に非常に多くのプロジェクトに携わり、様々な組織運営のパターンがあることを知っていたことも関係があったのかもしれません。
でも我々はこれまでどういう人の集まり方(組織)が理想的なのかということを学んだこともなければ、実験もあまりしてきていません。きちんと学び実践していけば、もっと理想的な組織のあり方が見えてくるのではないか、と漠然と考えていました。
例えばその時に考えたひとつのソリューションが『筋斗雲組織』です。アニメに登場する『筋斗雲』は、邪な心を持っていると乗りこなせません。それになぞらえて、良い理念・良い商品・人を大切にするという3つの要件がそろわないとうまく乗りこなせないという組織論です。それが実現すれば、営業や人事担当などがいなくても自然にうまく回るメカニズムができるのではないかという仮説が浮かびました」
そんなことを考えていたある日、仲間が職場で長時間雑談している様子を見てイライラしていることに気づいてしまう。事業をなんとか軌道に乗せようと効率性を重視するあまり、雑談という仲間にとって楽しい時間を自分は喜べない。この組織のあり方でいいのか、自分の中で何かが大きくズレ始めてしまっているのではないかと違和感を抱き、1年間休職して世界中を旅することに。その旅の途中で「ティール組織」に出合い、日本でも出版予定と聞いてぜひ手伝いたいと名乗り出た。そこからティールの探究が始まったのだ。
「個人としては素晴らしいのに、組織構造の中でくじけたり、想いをあきらめてしまう姿を見るうちに、『人類は組織のつくり方を間違えたのではないか』という問いが生まれました。学生時代に非常に多くのプロジェクトに携わり、様々な組織運営のパターンがあることを知っていたことも関係があったのかもしれません。
でも我々はこれまでどういう人の集まり方(組織)が理想的なのかということを学んだこともなければ、実験もあまりしてきていません。きちんと学び実践していけば、もっと理想的な組織のあり方が見えてくるのではないか、と漠然と考えていました。
例えばその時に考えたひとつのソリューションが『筋斗雲組織』です。アニメに登場する『筋斗雲』は、邪な心を持っていると乗りこなせません。それになぞらえて、良い理念・良い商品・人を大切にするという3つの要件がそろわないとうまく乗りこなせないという組織論です。それが実現すれば、営業や人事担当などがいなくても自然にうまく回るメカニズムができるのではないかという仮説が浮かびました」
そんなことを考えていたある日、仲間が職場で長時間雑談している様子を見てイライラしていることに気づいてしまう。事業をなんとか軌道に乗せようと効率性を重視するあまり、雑談という仲間にとって楽しい時間を自分は喜べない。この組織のあり方でいいのか、自分の中で何かが大きくズレ始めてしまっているのではないかと違和感を抱き、1年間休職して世界中を旅することに。その旅の途中で「ティール組織」に出合い、日本でも出版予定と聞いてぜひ手伝いたいと名乗り出た。そこからティールの探究が始まったのだ。
ティール組織のよくある誤解 「階層構造をやめればOK」ではない
著者のフレデリック・ラルー氏にアポを取って会いに行き、直接語らうほど「ティール組織」にのめり込み、組織の進化について学びながら実証し続けている嘉村氏。その魅力について聞いてみると、 「一番の魅力は『魂のこもった組織をつくれるか』を追求し、世界中で実例が数多く現れていること。仕事イコールお金を稼ぐ手段ではなく、仕事を通して自分達も顧客も社会もすべてが満たされることを本気でめざしている企業がある。そうした仕事に対する新しい価値観に感動しました」 そんな嘉村氏は現在ティール組織を広めるのではなく、ティールに対する正しい認識を広める活動をしている。例えばティール組織に関するよくある誤解として、「フラットな組織にすればいい」というものがある。 「ただ階層構造をなくせば良いというものではなく、ヒエラルキーとして存在していた権力が役割分担に基づく自然な階層構造に変わっていきます。新人とベテランでは専門性に差はありますし、リーダーシップを発揮する人もいれば、フォロアーシップがある人もいますから。ただ、こういった組織では一方的に命令したり、強制したりする関わりはほとんどなくなります。一人ひとりが組織の集合知を信頼して、助言し合いながら仕事を進めていきます。互いに仲間の力を活用しながら創造的に働けているならティールに近いと言えるのかもしれません。 また、ティール組織には失敗という概念はありません。行動したことによる学びがあるだけです。共通の目的に向けて安心安全な関係性の中で挑戦できる環境があるなら、ティールに近い組織と言えるでしょう。日本の大企業でも昔は本当につくりたいものほど上司の事前承認を取ることなく開発に挑戦する文化が根づいていたところもあったと聞いています。既にそうしたティールを取り入れられるフェーズにある企業がこの組織のあり方を参考にしてくれたらと思っています」 後編ではティール組織を自社に応用する考え方を、嘉村氏が自ら実践する組織作りの工夫と共に紹介する。
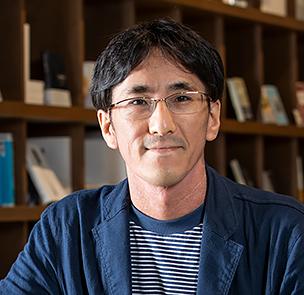
嘉村 賢州(Kamura Kenshu)
1981年生まれ、場づくりの専門集団NPO法人場とつながりラボhome's vi代表理事、東京工業大学リーダーシップ教育院 特任准教授。集団から大規模組織にいたるまで、人が集うときに生まれる対立・しがらみを化学反応に変えるための知恵を研究・実践。研究領域は紛争解決の技術、心理学、脳科学、先住民の教えなど多岐にわたり、国内外問わず研究を続けている。