仕事のプロ
百貨店とオフィスに共通する「人集め」の手法〈後編〉
回遊しながら気づきを得られる仕掛けづくりを

株式会社東急百貨店事業推進室参与の山田拓弥氏、学習院大学教授の河合亜矢子氏、コクヨ株式会社コンサルタントの伊藤毅の3人が、「集客戦略」を切り口に語り合う対談。後編では空間構築や設備にフォーカスし、百貨店とオフィスにおいて回遊や偶発的出会いを促すための手法について議論を展開した。
写真左から)伊藤毅、山田拓弥氏、河合亜矢子氏
「ついで」をつくることで 場に人を呼びやすくなる
伊藤:私たちは東京・品川のコクヨの自社オフィス「THE CAMPUS」で、ワークスタイルや環境構築などさまざまな実験を行っています。
その中でひとつ悩みどころなのが、「ついで」をどうつくるかです。ハイブリッドワークが当たり前になった今、在宅勤務中心の働き方を選ぶ人も増えています。それでも、「働くのは家でもオフィスでもよいけれど、「ついで」にやりたいことがあるから出社しようかな」と考えて出社するワーカーが増えれば、そこから新しい会話が始まり、イノベーションの種がまかれる可能性もあります。
東急百貨店様では、お客さまに「ついで」に来店していただくための仕掛けをどんなふうにつくっていらっしゃるのですか?
山田:例えば渋谷ヒカリエShinQsでは、館内に6カ所あるレストルームを「スイッチルーム 」と名付け、深海やオーロラをデザインした個室(ブース)があってプチトリップでバカンス気分のスイッチをオンにできる「Accent STAGE」や、ギャラリー空間を備えていて好奇心のスイッチをオンにできる「Style up STAGE」など、それぞれ異なるネーミングでコンセプトを表現しています。会員限定のパウダールーム やアート展示スペースを併設したりして、それぞれ異なる機能を持たせています。内装も、それぞれのフロアのコンセプトに合わせて変えています。
 山田拓弥氏
河合:「スイッチルーム」というネーミングの意図はどこにあるのでしょうか?
山田:日常から少し離れて気分を切り替えていただきたい、という思いから名付けています。それぞれのフロアのスイッチルームを訪れることで、自然と売り場を回遊することになり、商品やディスプレイに目を留めてもらえる機会が増えることも期待しています。
山田拓弥氏
河合:「スイッチルーム」というネーミングの意図はどこにあるのでしょうか?
山田:日常から少し離れて気分を切り替えていただきたい、という思いから名付けています。それぞれのフロアのスイッチルームを訪れることで、自然と売り場を回遊することになり、商品やディスプレイに目を留めてもらえる機会が増えることも期待しています。
偶然に出会うからこそ うれしさが高まる
伊藤:しかも ShinQsでは、2フロアごとに生活シーンに合わせて売り場を構成していらっしゃるので、お客さまにとっては「思ってもみなかった掘り出し物が見つかった」ということもありそうですね。
山田:まさに、現在のShinQsのコンセプトは、思いがけない発見や偶然めぐり会えた幸運を表す「セレンディップ」です。「お客さま自身に"新しいわたし "を見つけていただく」というイメージです。
河合:多数のブランド・メーカーの商品が集まっている百貨店の実店舗は、さまざまな商品を組み合わせて提示することによって、「サービス」を創造することができます。そこが単一ブランドの専門店と全く異なる点であり、百貨店の大きな強みです。さまざまな素材を使って、より自由に、「この場に来てよかった」という体験価値を創り出せるわけですね。
 河合亜矢子氏
伊藤:私も在宅ではなく出社して働く目的のひとつが、「誰かと話すこと」です。会議やミーティングではなく、意外な人と偶然出会えるとうれしさがあり、コミュニケーションが弾みます。百貨店で意外な掘り出し物を見つけたときの喜びと似ているかもしれません。百貨店における商品との偶然の出会いも、実は仕組まれたものなのでしょうか?
山田:仕組んだつもりでもそのようにいかないこともありますが、お客様の期待感に結び付けたいとは考えています。
河合亜矢子氏
伊藤:私も在宅ではなく出社して働く目的のひとつが、「誰かと話すこと」です。会議やミーティングではなく、意外な人と偶然出会えるとうれしさがあり、コミュニケーションが弾みます。百貨店で意外な掘り出し物を見つけたときの喜びと似ているかもしれません。百貨店における商品との偶然の出会いも、実は仕組まれたものなのでしょうか?
山田:仕組んだつもりでもそのようにいかないこともありますが、お客様の期待感に結び付けたいとは考えています。
内階段やエスカレーターも 「出会いの機会」として活用できる
伊藤:偶発的なコミュニケーションを引き出すことを目的に、「THE CAMPUS」の5~7階は内階段でつないでいます。内階段をフロアの中央につくるとそれなりに面積をくうのですが、階段を行き来するときに偶然顔を合わせたワーカーが話を始めることを期待してつくりました。
実際、このタッチポイントをきっかけにして部課を超えたコミュニケーションが生まれているようすがみられます。また、内階段を使うことによって自然と各階の執務スペースが視界に入るため、それぞれのフロアの利用者も増えています。
ただ気になっているのが、5・6階に比べて7階の「試す」というコンセプトを持つフロアの利用者がやや少ないことです。7階にはアトリエなどがあり、プロトタイプの制作などが行われています。しかし、専門性の高い作業が行われているせいか、このフロアに立ち寄るワーカーがあまりいないのです。
山田:確かに百貨店でも、お客さまがあまり立ち寄らないフロアに人を呼ぶ流れをつくるのには苦労します。
伊藤:そこで連想したのが、百貨店のエスカレーターでした。百貨店でエスカレーターを利用するとき、なんとなく「このフロアにはどんな商品が置いてあるのかな」と辺りを見回して、興味を引かれれば降りてみることもあります。
エスカレーター周りの空間を構築するにあたって、どんなことを意識していらっしゃいますか?
 伊藤毅
山田:エスカレーター周りの演出は重要ですね。エスカレーターサイドのスペースには、期間限定のポップアップストアを設置したりしてフロアの特色や変化を打ち出し、お客さまに回遊していただくためのきっかけとなることも目指しています。
伊藤毅
山田:エスカレーター周りの演出は重要ですね。エスカレーターサイドのスペースには、期間限定のポップアップストアを設置したりしてフロアの特色や変化を打ち出し、お客さまに回遊していただくためのきっかけとなることも目指しています。
リニューアル検討の前には 一定期間の観測で判断材料を集める定点観測が必要
河合:フロアにタッチポイントをいくつもつくることで、お客さまが思いがけない商品と出会う機会も増えていきますね。多くの百貨店ではオンラインショップも運営していますが、「思いがけないモノが目にとまる」「実際に見て、触って商品を選べる」というところは、実店舗だからこその利点だと感じます。 伊藤:オフィスの内階段周りにも、フロアの特徴を示すようなモノを展示したり、体験コーナーをつくったりした方がよいでしょうか? 山田:社員の方に気づきを提供し、「寄ってみようかな」と思わせるタッチポイントをつくれるといいですね。また百貨店では、売り上げやお客様の流れや支持など状況を、3年や5年などと見たうえで、その数値によってはコーナーやフロアのリニューアルも検討します。 伊藤:自社のオフィス構築においても、使用頻度が低いコーナーがあればコンセプト変更やリニューアル変更も考えます。お客さまにご提案する際も、期間を決めて使用状況を定点観測し、データをご覧いただいたうえでご一緒に検討するとよさそうですね。
フリーアドレスのメリットは 「正しい情報の筒抜け」にある?
伊藤:オフィスにも活かせる百貨店の空間構築や、サプライチェーンの観点から見た百貨店の実店舗の魅力について、たくさんのお話をいただきました。対談の最後に、山田さんと河合さんからご覧になって「THE CAMPUS」で印象的だった場所や機能についてお聞かせいただけないでしょうか? 河合:私は、新入社員が集まったり先輩と連携したりできる「フレッシャーズシート」に好感を持ちました。オフィス全体としてはフレキシブルに働ける中で、一部機能がフィックスされているコーナーがあるのがとてもいいですね。ここはワーカーにとって「出社したい」と思うフックになると思います。 さらに、「フレッシャーズシート」と同じフロアにある、上長のみなさんが集まるテーブルも印象的でした。自然とS&OP(販売事業計画;Sales and Operations Planningの略で、販売・生産・調達までの意思決定を早め、サプライチェーン全体を最適化する手法)のプロセスが補完できる潜在力を感じました。 山田:私は社員のみなさんがフリーアドレスの働き方をしているのを見て、「異なる部署の会議を小耳に挟む機会も多く、そこからの気づきも多いのだろうな」という発見がありました。 社内でも情報連携が行われていないケースは非常に多いので、周りの会話から「今知った情報や聴いた会話から考えると、私たちが策定しつつある戦略は見直した方がいいかもしれない」といったこともありそうです。機密性の高い情報は別として、フリーアドレスには「正しい(情報の)筒抜け」 というよさもあると感じました。 伊藤:コクヨでは25年以上フリーアドレスを採用しているので、自分たちでは改めて気づきにくいフリーアドレスのメリットをもご指摘いただけてありがたいです。 私たちはこれまで、さまざまな組織・企業様のオフィス設計やリニューアルを手がけさせていただき、「人が集まるオフィス」について自分たちなりの持論は持っています。 しかし今回、山田様から百貨店の集客戦略についてお話いただき、河合様にサプライチェーン・マネジメントの視点をいただくことで、さらに説得力のある空間づくりを実践していけそうです。今日は本当にありがとうございました。
【関連記事】百貨店とオフィスに共通する「人集め」の手法〈前編〉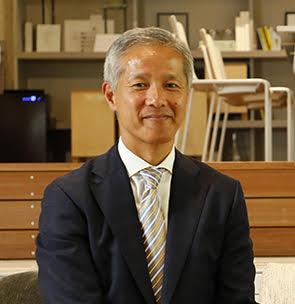
山田 拓弥(Yamada Takuya)
株式会社東急百貨店事業推進室参与。東急百貨店東横店やたまプラーザ店での店舗運営のほか、本社MD推進、営業政策、東急電鉄㈱(現東急㈱)リテール事業推進事務局、事業戦略室長などを経て現職。2012年に開業した「渋谷ヒカリエShinQs(シンクス)」ではコンセプト設計から開業一連に携わる。

河合 亜矢子(Kawai Ayako)
学習院大学経済学部経営学科教授。
筑波大学大学院システム情報工学研究科博士課程修了後、高千穂大学経営学部准教授などを経て2017年より現職。専門分野はサプライチェーン・マネジメント、オペレーションズ・マネジメント、経営情報システム。日本オペレーションズマネジメント&ストラテジー学会理事などを務める。共著に『グラフィック 経営学入門 (グラフィック経営学ライブラリ 1)』(新世社)、など、共訳書に『ビジネスゲームで学ぶサプライチェーンマネジメント』(同友館)などがある。

伊藤 毅(Ito Go)
コクヨ株式会社ワークスタイルイノベーション部部長。2007年コクヨ株式会社入社。2013年からワークスタイルコンサルタントとして従事。大企業のワークスタイル変革支援も行い、日経ニューオフィス賞経済産業大臣賞受賞など実績。コクヨ社内においては、「THECAMPUS」のICT統括担当として、ワークスタイルの設定および運用管理まで実施中。















