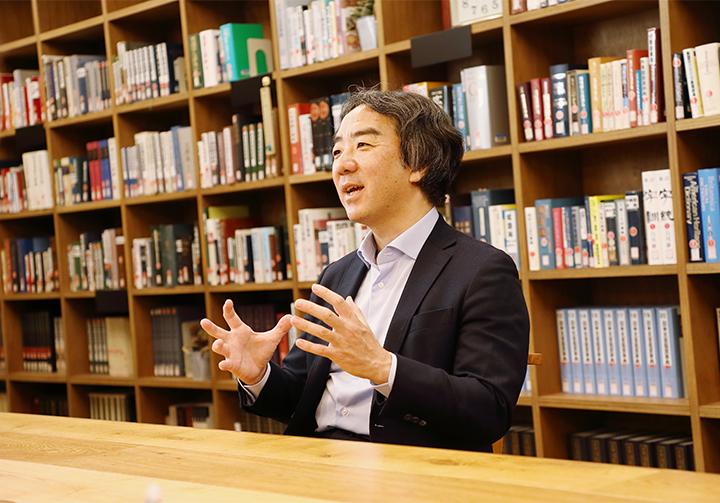仕事のプロ
多様な働き方に対応する、新しい「チーム」のあり方とは〈後編〉
これからのワークプレイスが果たす役割は?

リモートワークが浸透しつつある今、オフィスに求められるものやオフィスのあり方が根本から問い直されている。その背景には、チームワークやリーダーシップのあり方自体の変化があり、今後に向けて再考の時を迎えているのではないか。そんな問いをもとに、ウェルビーイング経営やジョブ・クラフティングを専門とする早稲田大学の森永雄太教授と共同研究者である日本大学理工学部建築学科の二瓶士門助教をゲストに迎え、コクヨのワークスタイルコンサルタントの坂本崇博を交えて対話を行った。
写真左から)二瓶士門助教、森永雄太教授
メンバー一人ひとりが、局面に応じて 「権限なきリーダーシップ」の発揮を
坂本:これまでの組織経営は分解型で、プラミッド構造の下、業務も上司・部下の関係性も個別に分けて考えがちだったと思うんです。一方、チームという単位は、リーダーはいても割とフラットな関係性なのかなと。チームにおけるリーダーについては、どのようにお考えですか? 森永:かつては先頭に立って指示を出し、組織を率いていく指示統制型のリーダーシップが主流でしたが、時代が変わり、昨今はチームの自立を促したり、インクルージョンを高めたりすることが求められるようになっています。 一方、指示統制型のリーダーシップを発揮しなくてはならないというリーダー自身の思い込みや、リーダーに対する「指示を出して導いてくれる人」という固定概念が根強いのが実情です。 そもそもリーダーシップのエッセンスは、「影響力を及ぼすこと」であり、本来は役職名ではありません。役職としてのリーダーとリーダーシップとは分けて考えるべきなんです。
 森永雄太教授
森永雄太教授
坂本:チームに影響力を与えるのがリーダーシップの本質、というわけですね。では、今後はどのようなリーダーシップが求められるのでしょうか? 森永:権限の有無に関わらず、チームのメンバー一人ひとりが自分ができる領域でリーダーシップを発揮するというあり方、いわば、権限のないリーダーシップです。例えば、タイムマネジメントが得意ならその局面ではリーダーシップを発揮し、他のメンバーがイニシアティブをとっているときはサポートに回る、といったあり方です。 坂本:メンバー一人ひとりがリーダーシップを発揮するためには、どのような素地が必要なのでしょうか? 森永:1つは、自己開示と心理的安全性ですね。早稲田大学のリーダーシップ開発の授業では、決して目立ちたがりやではない人や内向的な人であっても必要な場面でリーダーシップを発揮できるよう自分なりのリーダーシップを考えて実践する、というグループワークを行っています。 そこで大事にしているのが、チームビルディングに時間をかけること。どういうことが好きで何に興味があるのかといったポジティブな自己開示だけでなく、普段の生活の中でイライラ・モヤモヤすることを持ち寄り聴き合うというネガティブな自己開示もやっています。ちなみに後者は、どんな意見が出ても拒否せずにまずは受け止めるという、傾聴の練習にもなっています。
ゆとりあるウェルビーイングな働き方と 業務の効率化や業績アップは両立するか?
坂本:私自身も、お互いの自己紹介からレクリエーションまでチームビルディングにはかなり時間を割くタイプで、ゆとりある設計が大事だと考えています。 一方で、働き方改革やワーク・ライフ・バランスの文脈では、合理化、効率化、業務時間の削減が求められるなか、業務時間内にゆとりなんてない、という声も多く聞こえてきます。従業員のウェルビーイングとの兼ね合いも、難しいところだと感じています。
 坂本崇博
坂本崇博
森永:残業を減らすために忙しくなってしまい、ゆとりがなくなる...というのはよくあるパターンですよね。 私が研究している「ジョブ・クラフティング」は、自分に与えられた仕事を主体的に捉え直し、向き合い方を工夫することで、やりがいのある楽しい仕事に変えていく、という考え方です。 ジョブ・クラフティングが可能になると、仕事への主体性や意欲が高まり、結果的にウェルビーイングも高まるのですが、これもゆとりがないとできません。チームビルディングなども含めて業務全体の設計を会社や管理職が行うこと、そして、そこで生まれたゆとりを無駄にせず、有意義なジョブ・クラフティングに使うことが重要になります。 坂本:ゆとりも含めて、しっかり設計をしないといけないということですよね。 一方で、業績を伸ばさないといけない、稼がないといけないというプレッシャーから、ゆとりは削減されがちです。昨今は従業員のウェルビーイングにも注目が集まっていますが、効率アップ・業績アップとは相反する概念と捉えられがち。新しい融合の仕方はあるのでしょうか? 森永:ウェルビーイングの視点を経営に用いる際に大事なのが、長い時間軸で捉えることです。目先の業績アップではなく中長期的にアイデアが結実することを目指すべきであり、そこまで踏まえたうえで取り組まないと、「やったけど成果が出なかった」となってしまいます。 坂本:組織におけるチームは、ある目的のために形成された集団であり、思考の時間軸が短期になりがちですよね。いかにゆとりを組み込むか、あそびを内包するか、興味深いテーマです。
自分で選ぶ? 場の力を借りる? ワークプレイスの可能性を探
坂本:これからのチームやリーダーシップのあり方、そしてウェルビーイングについても対話をしてきましたが、これらを実現するためには、ワークプレイスとしてどのような場のあり方がふさわしいとお考えでしょうか? 二瓶:場所や空間の及ぼす影響は大きいという前提に立ち、選択肢をたくさん用意して、「使う人が選ぶ」というのが理想なんじゃないでしょうか。
 二瓶士門助教
二瓶士門助教坂本:まさにコクヨのTHE CAMPUSには、さまざまな形態のワークスペースや空間を設けて、社員が自分の好きな場所で仕事をしています。働きに来るというより、疲れたとき、孤独を感じたとき、社会とつながりたいと感じたときに来るオフィス。用事がなくても、仕事が休みの日にも、来たくなるオフィス。「CAMPUS」という呼称には、そんな想いも込めています。
 THE CAMPUSのフロア風景、右上から時計回り)PARK、BOXX、育むフロア、COMMONS
THE CAMPUSのフロア風景、右上から時計回り)PARK、BOXX、育むフロア、COMMONS
森永:「自分にフィットするワークプレイス」を自分で選べるというのは大事ですよね。 坂本:業務内容・目的や自分の好みに合った場所を選ぶという視点はありつつ、逆に、「場の力を借りる」という視点も面白いと思っています。 例えば、お気に入りの場所で仕事をすることで、億劫な業務もポジティブに捉えられたとか、リーダーだけみんなより低い椅子に座ってみたらなんだかチームの空気が変わったとか。 森永:坂本さんは先ほど、コクヨのオフィス(THE CAMPUS)にはプロジェクトごとの取り組みや実績を発表・発信する場があり、メディア的な役割を果たしているとおっしゃっていましたよね。デザインや設計の視点に加えて、こうしたメディア的な運用の視点も大事だと思います。 ワークプレイスで持続的にメッセージを発信することで、従業員のモチベーションを高めたり、チームのアイデンティティを醸成したりすることにつながると思います。 坂本:私たちはTHE CAMPUSでの実証実験やクライアントワークを通して、ワークプレイスについての知見を積み重ねてきました。一方、それを理論化・標準化できておらず、他にも応用できる再現性のあるものになっていないという課題があります。 今後はその部分について、森永先生や二瓶先生をはじめ研究者の方々と協力し、学術的な視点から探究していきたいと考えています。今後ともぜひ、よろしくお願いします。
【関連記事】多様な働き方に対応する、新しい「チーム」のあり方とは〈前編〉
森永 雄太(Morinaga Yuta)
早稲田大学グローバル・エデュケーション・センター
教授。神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。博士(経営学)。専門は組織行動論、経営管理論。著書に『ウェルビーイング経営の考え方と進め方 健康経営の新展開』(労働新聞社)、『ジョブ・クラフティングのマネジメント』(千倉書房、第39回冲永賞、第41回高宮賞)など。

二瓶 士門(Nihei Shimonn)
日本大学理工学部建築学科 助教。博士(工学)。一級建築士。
日本大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。北京新領域創成城市建築設計諮詢有限責任公司、飯田善彦建築工房勤務を経て、2012年に(株)バウ・フィジック デザインラボを設立。2013年より、日本大学理工学部建築学科所属。グッドデザイン賞など受賞歴多数。

坂本 崇博(Sakamoto Takahiro)
コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部/ワークスタイルイノベーション部/ワークスタイルコンサルタント/働き方改革PJアドバイザー/一般健康管理指導員
2001年コクヨ入社。資料作成や文書管理、アウトソーシング、会議改革など数々の働き方改革ソリューションの立ち上げ、事業化に参画。残業削減、ダイバーシティ、イノベーション、健康経営といったテーマで、企業や自治体を対象に働き方改革の制度・仕組みづくり、意識改革・スキルアップ研修などをサポートするコンサルタント。