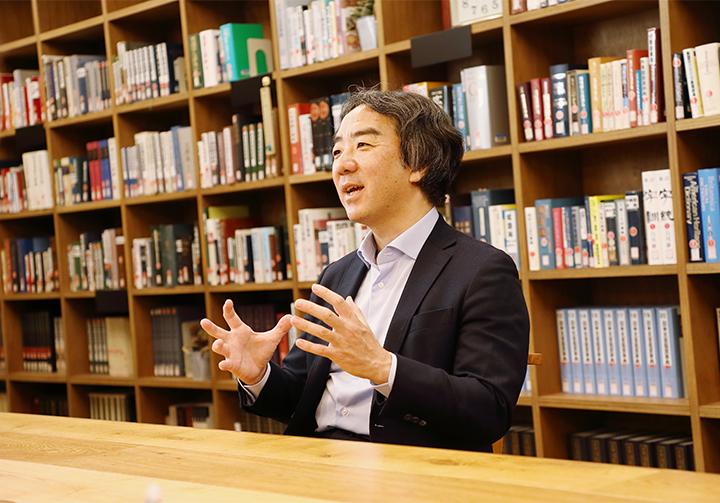仕事のプロ
多様な働き方に対応する、新しい「チーム」のあり方とは〈前編〉
今、ワークプレイスに求められるものとは?

リモートワークが浸透しつつある今、オフィスに求められるものやオフィスのあり方が根本から問い直されている。その背景には、チームワークやリーダーシップのあり方自体の変化があり、今後に向けて再考の時を迎えているのではないか。そんな問いをもとに、ウェルビーイング経営やジョブ・クラフティングを専門とする早稲田大学の森永雄太教授と共同研究者である日本大学理工学部建築学科の二瓶士門助教をゲストに迎え、コクヨのワークスタイルコンサルタンの坂本崇博を交えて対話を行った。
写真左から)森永雄太教授、二瓶士門助教
オフィスは従業員を巻き込んだ実験場。 模索して得られた知見を広く波及させたい
坂本:私たちコクヨは、東京・品川にあるオフィスを「THE CAMPUS(ザ キャンパス)」と呼称し、さまざまな実験的な取り組みを通して未来のワークプレイスや「働く」のあり方を模索してきました。 今日は、「チーム」というキーワードを軸に、オフィスの先にある可能性を共に探ってみたいと思います。まずは、森永先生と二瓶先生がどのような研究テーマに興味をおもちなのか、お聞かせください。 森永:私の専門は経営学で、職場のチームワークやリーダーシップ、ウェルビーイング経営に関心を持っています。現在は、経営学と二瓶先生の専門である建築学の間にあるテーマとして、「オフィス」に焦点を充てて共同研究をしています。 コロナ禍を経てオフィスのあり方や使い方が大きく変わるなか、二人でさまざまなオフィスを視察し、従業員へのアンケート調査なども行っています。
 森永雄太教授
森永雄太教授
二瓶:私が研究対象としてオフィスに興味をもったのは、実験場としての魅力があったから。例えば、コミュニケーションを促進するためにはどのような空間設計が有効かについて、いわば従業員を巻き込みながら実験しているわけです。物理的な環境が、人と人との関係性や心理にいかに影響するかは、建築学的にもとても興味深い視点です。ゆくゆくは、オフィス研究で得られた知見を、役所、大学、研究所、地域のコミュニティセンターなど、幅広い場所に波及させたいと考えています。
 二瓶士門助教
二瓶士門助教
自分やチームのアイデンティティに 「フィットするオフィス」という視点をもつ
坂本:昨今はABW(Activity Based Working)を取り入れる企業が増えていますが、ABWはもともとオランダが発祥の考え方で、集中して作業する、チームで会議をするなど、効率よく知的労働を行うためのシステムという意味合いが強いんですよね。 一方、これからのワークプレイスを考えるうえでは、カルチャーの醸成、ビジョンの浸透、従業員同士のつながりの創出といった感性や感情に関わる視点も重要ではないかと考えています。実際に、社内調査によると、「1日中同じ場所で仕事をしている人よりも、いろんな場所で仕事をしている人のほうがエンゲージメントが高い」といったデータも出ています。そのあたりについては、どのようにお考えでしょうか? 森永:二瓶先生との共同研究で関心をもっているのが、「オフィスが従業員にフィットしているか」という視点です。私たちは従業員を対象に、「美的(見た目の良さ)」「効率」「協働」「自分(たち)らしさ(アイデンティティ)」の4つの観点でオフィスの満足度調査を行いました。特徴的な結果として、自分らしさについては5段階評価のうち3(どちらでもない)という曖昧な回答が非常に多く収集されました。この結果から、「これまでオフィスには、自分らしさ、チームらしさ、会社らしさ...を表現したり感じたりする機能や機会がなかったからではないか」さらには「自分たちのアイデンティティを感じられるオフィスづくりを進めることに新しいオフィスの活用法の可能性が潜んでいるのではないか」と考えています。今後はさまざまな組織でデータをとり、この仮説を検証していきたいと考えています。 坂本:興味深いですね。なぜ、「自分(たち)らしさ」を指標の一つにされたのでしょうか? 森永:オフィスについて調査するなかで感じたのが、ABWを取り入れている組織でも、完全なフリーアドレスにしているところは少なく、多くが部署やプロジェクトチームごとのグループアドレスにしているということでした。実際、席がバラバラだとチームでコミュニケーションをとるのに不便、先輩が側にいない環境に放り込まれて新人が戸惑ってしまう...といった声をよく耳にします。 フリーアドレスを取り入れたことによりチームとしてのアイデンティティが崩壊したのではないか、ABWがうまく機能していないケースもあるのではないか、という問いが立ち、アイデンティティという指標を組み込むことにしました。 坂本:実は私は、未来のワークプレイスを、ABWに対して、発信するワークプレイス「WAM(Workplace As Media)」と名づけてみました。コクヨでは、仕事やワークスタイルに関して、部署単位だけでなく部署横断でもさまざまなプロジェクトが進んでいます。THE CAMPUSには、それらの取り組みや活動実績を発表・発信できる場や機会を設けています。これなどはまさに、チームとしてのアイデンティティの醸成につながっているかもしれませんね。
 坂本崇博
坂本崇博
メンバー同士が多様につながる 自立したチームが組織を支える
坂本:では、これからの働き方を考えるうえで、「チーム」はどうあるべきだとお考えですか? 森永:昨今は、ダイバーシティやインクルージョンの視点から、チームのメンバーの個が尊重され、1on1などのケアも浸透しています。一方、上司や管理職がすべてを担うことで疲弊してしまい、管理職につきたくないという層も増えています。 負担が偏ることなくチームとして自立するためには、上司と部下という縦方向だけでなく、チームのメンバー同士という横方向の関係性も含めて、いろいろなスタイルでモチベーションのメンテナンスや個性の引き出しをやるべきではないか、それはオフィスのしつらえにも関係するのではないか、と考えています。 坂本:先に述べたコクヨの社内プロジェクトを通しても、横方向の関係性が生まれています。一体感があるチームだと、みんなで一緒に頑張ろうとか、周りが頑張っているから自分も頑張らなきゃとか、ソーシャルな部分でモチベーションが高まりますよね。まさに、切磋琢磨するということなのでしょう。
 THE CAMPUSの屋上ガーデンを見学
THE CAMPUSの屋上ガーデンを見学
二瓶:私の研究室には学生が25人ほどいて、昨年までは私が一人で全員と1on1をやっていたのですが、これが相当大変で...。今年からはやり方を変え、学生同士でチームを組んで、論文を書くための基礎やちょっとした課題などはチームで解決するよう任せました。私と学生の1on1もやりつつ、プロジェクトごと、研究テーマごとなどのいろいろな単位でチームを組むことで、一人の学生でも見えてくる側面が違ってきます。私自身も楽になり、組織と個人の幸せをつなぐ単位としての「チーム」の大切さを実感しています。 坂本:複数のチームに所属して異なるつながりや役割をもつことって、やはり大事なんですね。 二瓶:情報学の研究によると、通い慣れたお店や期間限定のプロジェクトチームなど、「離脱可能なコミュニティ」に多く所属することで人生が豊かになるという結果があるそうです。一方、容易に離脱できない会社や家族といった結束の固いコミュニティも大切で、そこでは個人の多面的な断面が見えるよう、大小さまざまなチームをつくることが大事なのではないかと思います。 後編では、リーダーシップやウェルビーイングの観点から働き方やワークプレイスについて語り合います。
【関連記事】多様な働き方に対応する、新しい「チーム」のあり方とは〈後編〉
森永 雄太(Morinaga Yuta)
早稲田大学グローバル・エデュケーション・センター
教授。神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。博士(経営学)。専門は組織行動論、経営管理論。著書に『ウェルビーイング経営の考え方と進め方 健康経営の新展開』(労働新聞社)、『ジョブ・クラフティングのマネジメント』(千倉書房、第39回冲永賞、第41回高宮賞)など。

二瓶 士門(Nihei Shimonn)
日本大学理工学部建築学科 助教。博士(工学)。一級建築士。
日本大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。北京新領域創成城市建築設計諮詢有限責任公司、飯田善彦建築工房勤務を経て、2012年に(株)バウ・フィジック デザインラボを設立。2013年より、日本大学理工学部建築学科所属。グッドデザイン賞など受賞歴多数。

坂本 崇博(Sakamoto Takahiro)
コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部/ワークスタイルイノベーション部/ワークスタイルコンサルタント/働き方改革PJアドバイザー/一般健康管理指導員
2001年コクヨ入社。資料作成や文書管理、アウトソーシング、会議改革など数々の働き方改革ソリューションの立ち上げ、事業化に参画。残業削減、ダイバーシティ、イノベーション、健康経営といったテーマで、企業や自治体を対象に働き方改革の制度・仕組みづくり、意識改革・スキルアップ研修などをサポートするコンサルタント。