2025.06.27
【自治体のヨコクフェア!?】レポート(1)
これからの働き方と庁舎の未来
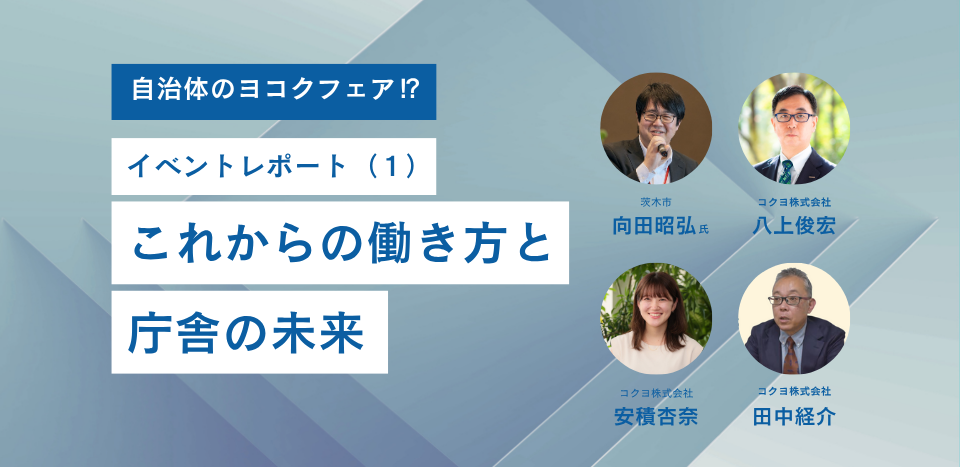
Overview
概要
2025年5月20日「自治体のヨコクフェア!?」と題した自治体職員向けイベントがコクヨ梅田ライブオフィスで開催されました。コロナ禍を経て、DXはますます加速し、自治体の窓口のあり方や、職員の働き方は、大きな転換点を迎えています。また、住民の行政参画や官民共創の動きが活発になっている背景もあります。そこで今回のイベントでは、窓口改革や庁舎リニューアルの先進事例、市民の共創拠点となっている「おにクル」の取り組みをご紹介。さらに最新のオフィスツアーを通じて、これからの働き方や庁舎の未来について、参加者のみなさんとともに考えていきました。
第1部
・ 講演1 フロントヤード改革によるこれからの窓口
・ 講演2 先進事例に学ぶ 庁舎空間リニューアル
・ 講演3 「おにクル」に学ぶ 市民共創の実現と挑戦
第2部
・ コクヨ梅田ライブオフィス見学ツアー
Report
レポート


住民との「接点」として、フロントヤードのあり方を再定義する
「スマートフォンで60秒ですべての行政手続きが完了する社会」これは、行政デジタル化の目標像であり、その実現に向けて、政府は①すべての手続きをデジタルで完結させる「デジタルファースト」、②複数の手続きを一か所で済ませる「コネクテッド・ワンストップ」、③一度提出した情報は再提出させない「ワンスオンリー」という三原則を掲げています。
これらの基本方針を踏まえ、総務省は2023年に「自治体DX推進計画3.0」を策定。その中で重点項目として位置づけられるのが「フロントヤード改革」であり、3つのコンセプトが掲げられています。まずは、マイナンバーカードを活用し、公民館や郵便局、自宅などでも手続きが可能となる「接点の多様化」。次に、紙の申請書を使わず、すべてをデータで処理する「デジタル対応」。そして、窓口を単なる手続きの場から、民間企業やNPOなどさまざまな主体と行政が連携する「協働の場」へと変えていく「空間の再定義」です。
フロントヤード改革を進める際には、現在の業務をそのままデジタル化するのではなく、まずムダや過剰、非効率な部分を見直すことが重要です。そして、理想の窓口の形を決めたうえで、業務フローや組織構造を再構築し、バックヤードも含めた窓口業務の改善を行います。その後、必要なシステムを整え、そのシステムを効率的に使える庁舎の空間を考えます。これにより、「書かない」「迷わない」「待たない」窓口、最終的には「行かない」窓口を実現することを目指します
改革の過渡期だからこそ、フロントヤードには「可変性」が必要
フロントヤード改革は段階的に進める必要があり、将来的な変化を見据えた柔軟かつ継続的に対応できる空間構築が求められます。
2024年1月に書かないワンストップ窓口を導入した桑名市や2025年5月に市役所の窓口機能を集約した新施設「寝屋川市サービスゲート」をオープンした寝屋川市は、将来の用途転換に対応できる什器や運用を取り入れ、柔軟に対応できる窓口空間を構築しています。
桑名市や寝屋川市などを含む15自治体の窓口改革事例をまとめた資料をご用意しています。これからの窓口および庁舎空間づくりの参考として、是非ご活用いただければ幸いです。
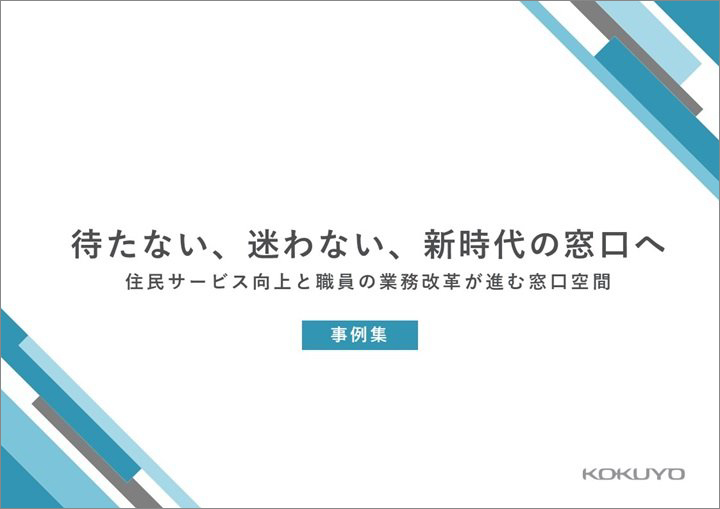
講演2では、「先進事例に学ぶ庁舎空間リニューアル」と題し、コクヨTCM営業第1部の田中経介より自治体におけるオフィス改革の実践的な進め方について、多数の事例を交えて紹介しました。

オフィス改革は、「これからの働き方」を実現する起点となる
地方自治体が抱える喫緊の課題として、「若年層の早期退職」「採用応募者数の減少」「内定辞退者数の増加」があります。背景には労働人口の減少と、働き方の価値観の多様化があり、こうした変化に対応するためには、「職員が仕事に対してポジティブで充実した状態=ワークエンゲージメントが高い状態」で働ける環境を提供することが必要です。そのためにも組織文化、マネジメントスタイル、職員マインドの変革が重要であり、「オフィス改革はそうした変化を生み出すための起点」になります。
また、今後の行政業務は、AIや外部委託の活用で定型業務が削減される一方、前例にとらわれることのない「価値創造型」の業務が増えていくと考えられ、オフィス改革を進める際には、現状の課題解決を目指す「フォアキャスティング」型ではなく、理想の働き方から逆算して空間・制度を整備する「バックキャスティング」の考え方が有効です。
さらに、重要なキーワードとして挙げられるのが「スモールスタート」です。まずはパイロットオフィスからはじめ、段階的に複数の部署へと展開し、最終的には全庁へと広げていく。そうしたステップが、着実な改革に結びついていきます。
こうしたアプローチを実践した庁舎リニューアルの先行事例として、愛媛県西予市や熊本県庁、奈良県庁などの取り組みを紹介。どの事例にも共通するのは、単なる制度変更にとどまらない「文化とルールの見直し」が改革の根幹にある点です。「当たり前を問い直すことこそが、今後の庁舎づくりの鍵」になります。
第1部の講演の最後に登場したのは、茨木市市民文化部 共創推進課の向田昭弘氏です。2023年に開館した同市の子育て複合施設「おにクル」について、その背景や市民共創の取り組みについてお話しされました。

市民との対話を通じて、進化を続ける「おにクル」
「おにクルは、市民会館の建て替えを契機に、「ゼロベースで、市民と対話しながら育てていく」という方針のもと整備された施設です。施設名は公募により6歳の男の子のアイデアが採用され、ほかにも設計段階から多数のワークショップや、社会実験を重ねてきたといいます。
現在は年間約200万人が訪れ、1階オープンスペースの年間イベント利用数は768件を超えるという同施設。「完成ではなく、使いながら育てていく」ことを前提とした柔軟な運営が特徴で、市民との対話を通じて、今もなお進化を続けているといいます。おにクルの取り組みについては、次回のレポートでさらに深掘りしていきます。
講演終了後は、第2部として、コクヨ梅田ライブオフィスの見学ツアーを開催しました。コクヨ社員が実際に働く姿を見ていただき、ツアーに参加されたみなさまからも「庁舎リニューアルや働き改革のヒントになるかも」と、嬉しいお声をいただきました。

