2025.07.27
【自治体のヨコクフェア!?】レポート(2)
進化を続ける「おにクル」
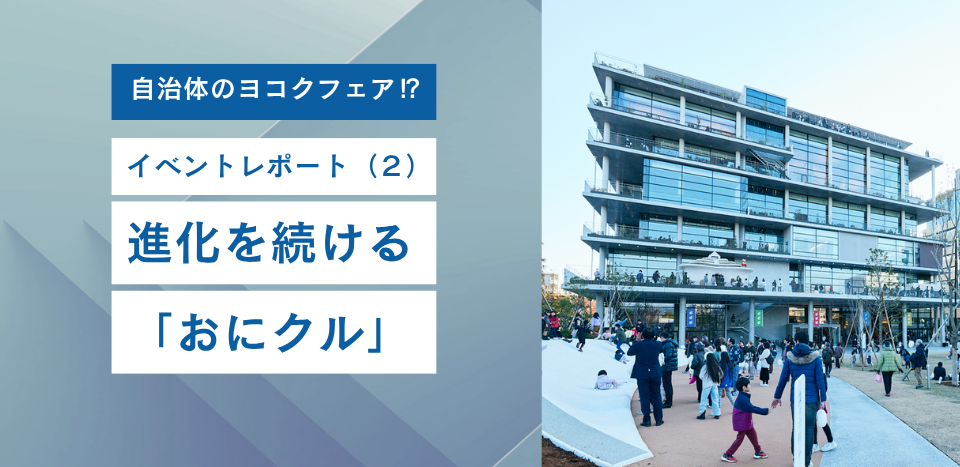
Overview
概要
2025年5月20日、コクヨ梅田ライブオフィスにて開催された自治体職員向けイベント「自治体のコクヨフェア!?」。自治体の窓口のあり方や、職員の働き方をテーマに、先進的な取り組みや事例が紹介されました。今回のレポートでは、そのなかでも市民との「共創の拠点」として注目を集める、大阪府茨木市の「おにクル」にフォーカス。施設の立ち上げから運営に携わる同市市民文化部 共創推進課・向田明弘氏による講演の模様をお届けします。
Report
レポート
「正解」を求めるのではなく、みんなで「育てる広場」を
2023年にオープンした「おにクル」は、ホールや図書館、子育て支援、市民活動センター、プラネタリウムなど、多くの機能を備えた文化・子育て複合施設です。年間の来場者数は、約200万人。施設1階のオープンスペースの年間利用数は768回にものぼります。
「おにクル」が位置するのは、JR茨木駅と阪急茨木市駅の両駅を結ぶ「東西軸」と、元茨木川緑地の豊かな自然が広がる「南北軸」が交わる、まちの中心部。同市では以前より、「ウォーカブルなまちづくり」を進めるために、このエリアをどのように整備するかが課題となっていました。なかでも焦点になっていたのが、2015年に閉館した茨木市市民会館の跡地の活用方法です。
向田氏:そんなとき、当時就任したばかりの福岡市長が提案したのが、市民と対話しながら、ゼロベースで新たな場をつくっていこう、ということでした。
そこで最初に取り組んだのが、「市民会館100人会議」というワークショップです。無作為抽出された100人の市民が、毎回10人ずつ、10回にわたって市長と直接対話。跡地の活用のあり方や、まちの未来について語り合いました。そのなかで生まれたさまざまなアイデアを事務局メンバーが集約。新たな施設に求められる機能を絞り込んでいきました。

向田氏:ところが、ある程度の方向性が見えてきたところで、市長から『これで市民は幸せになるのか?』と、問いかけられたんです。つまり、新たな施設をつくることで、市民の暮らしはどう変わるのか。それを考えなければ、結局は単なる“箱物”になってしまうのではないか、と。最初は頭を抱えましたが、振り返って見るとこれが大きな転機となりました。
この問いをきっかけに、100人会議から生まれたアイデアを見直すなかで見えてきたのが「同じ市民でも、人によって新たな施設に求めるものはまったく異なる」という事実です。そんなシンプルながら本質的な気づきを前に、事務局メンバーが選んだのは「あえてひとつの正解を求めない」という選択肢でした。
向田氏:そもそも、私たちがいくらそれらしい『正解』を示したところで、それが10年後も通用する保証はありません。時代が変われば、当然、市民のニーズも変わっていきます。それならば、この場をどう使い、どう活動し、どう変えてゆくのかを、最初から市民に委ねてはどうだろうか。そう考えたんです。
それを誰もが共感できるかたちで言語化したのが「育てる広場」というキーコンセプトです。つくって終わりではなく、市民とともに育ち続ける場でありたい。基本構想から運営に至るまで、おにクルの指針となっている考え方です。
小さく「試してみる」ことで、まちのプレイヤーが増えていく
「育てる広場」というキーコンセプトのもと、「対話」からさらに一歩進んだ「参加」へとつなげるために、設計段階に入ってからも、市民参加型の多種多様なワークショップを実施。その回数は合計108回にのぼり、延べ参加者数は2000人以上に達しました。
向田氏:たとえば、工事現場に子どもたちを招き、みんなでタイルを貼る、という体験型のワークショップを開催しました。ほかにも設計事務所を巻きこんで、市民が設計スタッフと一緒になって施設のデザインや仕掛けを考える、という企画も実施。すると設計側も市民の声を聞けるし、市民の側も自分たちの声がかたちになったという実感が得られる。両者にとって、とても意義のある取り組みになったと感じています。

とはいえ、市民の参加を促せばそれでうまくいく、というわけではありません。幅広い意見が集まる一方で、それらをひとつの方向にまとめていく難しさにも直面しました。そこで、ワークショップと並行して行われたのが、「市民の声を聞く」だけでなく、「実際にやってみる」ことを重視した社会実験です。
その舞台となったのが、「IBALAB@広場」という期間限定の広場でした。ここでは、新しい施設の使い方を試してみたり、一人ひとりが「やってみたいこと」を小さくはじめてみたり、公共空間を「使う視点」で見つめ直すさまざまな取り組みが実施されたといいます。
向田氏:IBALAB@広場には、スケートボードやボール遊び、花火など、普通の公園では禁止されているようなことが、どうすれば「できる」のかみんなで考えました。ときには利用者同士で意見がぶつかることもありますが、それを話し合いによって乗り越え、自分たちで“ルールをつくる”という経験をしてもらうことも、この広場の大きな狙いのひとつでした。

「IBALAB@広場」での社会実験を通じて、やがて自ら企画を立ち上げ、実行する人たちも育っていきました。現在、おにクルが市民や事業者、行政といったステークホルダーが垣根を越えてコラボレーションする「共創の中心地」となり得ているのも、オープン前からこの場所を拠点に活動してきた地元の「プレイヤー」たちの存在があったからです。
「共創」を生むために大切な4つのポイント
講演の最後には、おにクルでの一連の取り組みを通して、向田氏自身が感じた「共創を生み出すためのポイント」が、4つの視点から整理されました。

まずは「クラフト」。完成された場所やルールを提供するのではなく、みんなが手をくわえられる「関わりしろ」をあえて残すことで、さまざまな人が自分たちの手で公共空間を育てていけるようになります。たとえば、おにクルでは、駐輪場の使い方についてみんなで話し合うなかで、「フェンスやラックではなく、花壇で駐輪スペースを示す」というアイデアが生まれました。
2つめは「コーディネーター」。異なる立場の市民をつなぐハブとなる人がいることで、アイデアが交差し、ときに意外な化学反応が生まれます。盆踊りとDJが融合したイベントは、その好例といえるでしょう。
3つめは「コモンズ(共有地)」です。行政は場をひらき、市民は楽しみながら運営に参加する。困りごとがあったときも、行政に任せるのではなく、みんなで一緒に考え、ともに行動する。そうした経験を通じて、公共地でも私有地でもない「コモンズ」という場の捉え方が、少しずつ根付いていくといいます。
そして最後が「コミュニケーション」。市民だけでなく、市の職員同士の横のつながりも含めて、「一緒にやる」という意識を持つこと。管理する側・される側という上下の意識を乗り越え、誰もが互いに尊重し合い、フラットな関係を築いていくことの重要性が、強調されました。実際に施設内では、利用者同士の声かけのきっかけをつくる「おにの気持ち」という取り組みをはじめ、日々のコミュニケーションを大切にする姿勢が実践されています。

向田氏:こうしたポイントを意識しながら場づくりを進めることで、はじめて生まれるのが「共創」ではないでしょうか。おにクルという場を介して、誰もが楽しみながらつながれる。そんな場所を、これからもみんなで育てていきたいと思います。