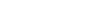はじめに:組織開発の潮流変化
組織開発の考え方は、時代とともに大きく変化してきました。かつては「組織図」を描き、役割と権限を明確にすることで、「設計通りに機能する枠組み」にすることが中心でした。しかし今、私たちが直面しているのは、まったく異なる状況です。
今後組織開発において重要になるのは、「目的達成のための各種機能・役割設計」の中で、「組成後の状況変化に柔軟に対応しながら、チームやメンバーが共に持続的に成長し、新たな提供価値を生み出し続ける組織成長のフレームワーク」を強く意識していくことだと考えています。
私たちが目指すべき理想のチーム像
多くの企業が目指す理想のチーム像とは、次のような姿ではないでしょうか。
掲げる目的・成果に向けて、メンバー個々人が自律的かつ主体的に、仕事と自分の未来に期待を持って取り組んでいる。そしてチーム全体として、メンバーの多様な力を活かしながら常に成長し、独自の強みや提供価値を生み出している。
この理想像を言葉にするのは簡単ですが、実現することは簡単ではありません。なぜなら、私たちを取り巻く環境が、この瞬間も劇的に変化し続けているからです。
組織開発を取り巻く環境変化
コロナ禍を経て、私たちの働き方や意識は大きく変わりました。リモートワークが普及し、「オフィスに集まること」の意味が問い直されはじめています。また、VUCA時代と呼ばれる予測不能な市場変化の中で、かつて通用していた「正解」を前提としたビジネスモデルは通用しなくなっています。
さらに、少子高齢化による人材不足に加え、人的資本経営への注目の高まりにより、従業員一人ひとりの能力や可能性を最大限に引き出すことが、企業の競争力を左右する時代に突入しています。同時に、エンゲージメントの向上やDE&I(多様性・公平性・包括性)の推進、さらにはDXの加速なども、新たな組織のあり方を模索する動きとして急速に広がっています。
一方現場が直面している課題もより複雑かつ多様化しています。たとえば、優秀な人材の突然の離職、社員の価値観やニーズの多様化、そして「やりがい向上施策」の効果が不明瞭など。人事部門の方々からは「なぜ社員が辞めるのかわからない」「何をすれば、社員はやりがいを高められるのか」という悩みの声をよく耳にします。
私たちコクヨは、長年にわたりお客様のオフィス構築と働き方改革に寄り添わせていただいている中で、「働き方」のみならず、「働くこと」そのものの意味や価値観の激変を、お客様と共に現場で体験してきました。それらの経験から見えてきた組織開発の課題と可能性について、お伝えしていきたいと思います。
組織開発の新たな枠組み

働き方が多様化した今、メンバー一人ひとりが「チームに求めること」と、会社として「チームに求めること」は大きく異なり始めています。端的に言うと、「会社は成果を求め、個人は成長や働きがいを求める」というギャップが、驚くほど大きくなっていると言ってよいでしょう。
そんな今、過去に設計した仕事に淡々と対応していくだけの「過去の組織開発」では、チームもメンバーも as is(現状)的な成長しかできません。これから求められるのは、チームとメンバーが共に仕事と自分の to be(あるべき姿)を描き、重ね、バックキャスティングで現場課題に取り組んでいく、「新しい組織成長フレームワークの現場実装」が必要です。
現場チームの実態にあわせて具体的な問題や課題要素を見定めることができる、言い換えると「チームごとの特性に合わせた、成果・成長の道筋を描ける」新しい考え方・枠組みが求められていると言ってよいでしょう。
これからの組織開発に求められるフレームワーク
今後の組織開発において、改めて「目的達成のための機能・役割設計」を、次の2つの枠組みで捉える、組み合わせて推進していくことを提案します。
実務実行フレームワーク:与えられた資源・資産を使い、チームが業務成果を挙げるために実行する実務と管理のフロー・役割・手順の設計
組織成長フレームワーク:チームの目的への合意と、メンバー間の相互理解・協働意識・経験拡張を通じた、チームとメンバーの持続的な成長の設計
従来の個人の能力開発や1on1などの1人ひとりへの対応は、実は「実務実行フレームワーク」の中の管理のひとつ、とは言えないでしょうか。これからは「組織成長フレームワーク」としてしっかりと、チーム全員で「目指す姿・理想のチーム状態」、そして「そこで実現したい未来の自分像」を描き、相互の成長計画を重ね合って、そのための具体的課題に取り組むことが望ましいと考えます。
「実務実行フレームワーク」と「組織成長フレームワーク」という2つの視点を意識的に組み合わせていくことこそが、「令和の新しい組織開発」の姿と言えるでしょう。この新しいアプローチは、チームの生産性向上だけでなく、メンバー一人ひとりの成長実感を醸成し、エンゲージメント向上にもつながっていくーーーまさに、成果と成長の両立を実現する筋道だと言えるでしょう。
まとめ:組織成長に向けた第一歩
ここまで、これからの時代に求められる組織開発・組織成長の新たな考え方をお伝えしてきました。とはいえ、「具体的にどう実践すればいいのか?」という疑問を抱かれた方も多いのではないでしょうか。
実は、このフレームワークを現場で実践するためには、いくつかの重要な背景理論の再解釈や現場実行のステップ、具体的なツールが必要になります。それらについては、次回以降のコラムで詳しくお伝えしていく予定です。
また、今回ご紹介した考え方を実践している弊社事例はもちろん、先行して共感をいただき、開発ご支援を賜りましたお客様企業の実践事例も今後ご紹介していきます。エンゲージメントスコアなどの指標がどのように変化したのか、定量・定性的な効果分析の結果についても、順次お伝えしていきます。
私たちは今、組織開発の大きな転換点に立っています。単に「組織・チームを変える」というのではなく、解像度を上げ「組織・チーム自体が、成長する力を自ら作り上げていく」という発想が、これからの時代に不可欠だとな組織づくりの鍵だと考えています。
「チームの力は個人の総和を超える」という言葉があります。しかし、それは自然発生的に実現するものではありません。時代と状況に合った、意識的な組織開発の取り組みがあってこそ実現するものです。皆さまの組織やチームが、メンバーと共に持続的に成長していく「理想のチーム像」に向けて、お役に立つことができましたら嬉しく思っております。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに。
注釈:
-
本コラムでは、「組織」は「会社組織図上の様々な役割の集合体」を、「チーム」は同じ目的のもとで実務を分担・連携し合う「10名前後の集団」を指しています。
-
VUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、予測困難な社会状況を表します。
-
DE&I:Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包括性)の略称です。
-
バックキャスティング:目標となる未来の姿から逆算して、現在何をすべきかを考える思考法です。
-
as is / to be:現状(as is)と目指すべき姿(to be)を明確にし、そのギャップを埋めるための計画を立てるアプローチです。
-
人的資本経営:人材を「コスト」ではなく「資本」と捉え、その価値を最大化することで企業の持続的成長を目指す経営手法です。2022年8月に経済産業省から「人的資本可視化指針」が公表され、企業の人的資本への投資・開示の重要性が高まっています。

組織成長ソリューション
TEAMUSを
もっと知りたい方へ
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフがさらに詳しく
機能についてご説明いたします。