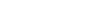目次
「はたらく」の意義が変わる時代
私たちコクヨは長年、オフィス環境の構築を通じて多くの企業の「はたらく」をサポートしてきました。その中で明確に感じたのは、「はたらく」に求められる意義の大きな変化です。
ハイブリッドワークなどの勤務形態の変化だけではありません。企業がオフィス投資をする際のコンセプトを見ると、今や「やりがい」「成長実感」「一体感」「風土醸成」といったキーワードが中心を占めています。
つまり、給与や地位だけでなく、体験価値やそれを支える組織文化が今まで以上に重要視され、それらが企業競争力の源泉になっているのです。
組織文化学の第一人者エドガー・シャインによれば、組織文化は3層で構成されています。*1
-
「人工物」:組織図、オフィスなど目に見えるもの
-
「価値観」:言語化されている理念、ビジョン、パーパス
-
「基本的仮定」:無意識に当たり前になっている思考や行動原理
真の成長や変革には、最も深層にある「無意識の思考や暗黙の了解」を変えていく必要があります。
では、この見えにくい組織状態や成長度合いはどのように計測し、戦略や施策に反映すればよいのでしょうか。この問いが、私たちのサービス開発の出発点となりました。
経営・人事・現場のギャップと分断の危機
様々な立場の方々との対話を重ねる中で、驚くべき事実が見えてきました。先進的と見なされている大企業であっても、組織文化や成長度合いを測る有効な手段がほとんど存在していないのです。
さらに深刻なのは、立場の違いによるギャップが各所に生じていることでした。組織内の連携が進まないだけではなく、分断の危機さえあったのです。
経営層の声:
-
「経営戦略と具体施策が一致していない。現場の理解や協力が得られない」
人事部門の声:
-
「様々な調査をしているが、いつの間にか満足度調査ばかりになっている」
-
「問題部署への対処に手一杯で、成長議論ができない」
-
「個人の多様な事情を全体施策ではカバーしきれず、不満が溜まっている」
-
「現場リーダーへの人事業務期待が大きくなり、負荷が集中している」
現場の声:
-
「高度なリーダーシップを求められるが、習得は我流のまま」
-
「リーダー任せで、全体最適の思考ができるメンバーが育たない」
-
「人事施策に協力しても、何がよくなるのか実感できない」
-
「組織文化や未来について話す機会がなく、自分事にならない」
企業と個人が共に成長していこうという取組みであるにも関わらず、組織内の分断や諦めを生んでいる。この問題に向き合うために、私たちが着目したのが「チーム」という存在です。
「チーム」が組織と個人をつなぐ架け橋に
組織成長のアプローチには、経営層からの「トップダウン型」と社員個人からの「ボトムアップ型」があります。しかし両者にはそれぞれ長所と短所があります。
トップダウン型は社員の納得感や当事者意識を得にくく、ボトムアップ型は現場負担が大きく、方向性の一致も困難です。
そこで私たちは、両者をつなぐ「ブリッジ型」のアプローチとして、「チーム」単位での成長に注目しました。
この視点で改めて見てみると、チームとは不思議な存在です。半分は自分自身でありながら、半分は自分ではない。この絶妙な距離感が、個人の思いと企業の方針の目線を合わせ、主観と客観を交えた対話を生み出します。
さらに、チームは事業と直結した業務推進の単位でもあります。チームが成長すれば、企業の競争力向上に直接寄与するのです。
実際、経済産業省の社会人基礎力においても「チームで働く力」は重要な能力として位置づけられています。グーグルの研究では、心理的安全性や相互の関わり方が生産性に大きな影響を与えることが証明され、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスも小規模チームの重要性を説いています。*2
個人にとっても、やりがいや成長実感などの多くは「誰かとの関わり」の中で生まれる感情的報酬です。
このように、チームは組織と個人をつなぐ最適な単位であることから、私たちは「TEAMUS(チームアス)」の開発に着手したのです。
TEAMUSが実現する成長の好循環
TEAMUSの名前には「未来に向かって、自分たち自身で、チームのチカラを引き出す(Team + Us=わたしたち・明日)」という意味を込めています。
チームの今と未来を見つめることで対話と内省を生み、相互理解を深める。気づきや刺激を与え合いながら、より大きな成果を生み出していく。そんなチームからはじまる成長サイクルを未来へつなげていきたいのです。
TEAMUSのコアは、マサチューセッツ工科大学組織学習センター共同創始者のダニエル・キム氏が提唱した「成功循環モデル」にあります。*3
これは「関係の質」→「思考の質」→「行動の質」→「結果の質」というつながりを重視するモデルです。良い結果はさらに関係の質を高め、好循環を生み出します。言い換えれば、結果だけを強引に求めても持続的な強さは生まれないということです。
TEAMUSではこの好循環を「わかる・気づく・変わる」の3ステップでサポートします。
わかるステップ:
チームコンディションサーベイで、チームの実態・実力値を把握します。関係・思考・行動の各フェーズにおいて、「チームづくり」「連携の促進」「成長への挑戦」という3レベルでの達成度と課題を可視化します。
-
「チームづくり」:自部門で業務を円滑に回せる段階
-
「連携の促進」:部門をまたいで連携できる段階
-
「成長への挑戦」:他部門を巻き込み新企画を推進できる段階
気づくステップ:
専門スタッフとチームリーダーの対話を通じ、サーベイでは捉えきれない現状や改善ポイントを把握します。リーダーの意識変容を促し、チーム成長のきっかけを作ります。
変わるステップ:
ビジネスコーチによる伴走プログラムで、具体的な行動変容を促します。表面的な診断にとどまらず、リーダーの実行力を育み、チーム全体の変化を支援します。
未来のチームが変える「はたらく」の景色

TEAMUSを通じて私たちが実現したいのは、企業にとって「強いチーム」が、働く人たちにとっては「人生最高のチーム体験」が次々と生まれる社会です。
組織文化も与えられるものではなく、一人ひとりが参画し、主体的に作り上げていくものへと進化します。できていないことを指摘するだけではなく、できる可能性を信じ、それを発見していく。そうした前向きな姿勢がチームの力を最大限に引き出します。
TEAMUSは、そんな未来への第一歩です。チームから、個人と組織の持続的な成長をサポートすることで、日本中の「はたらく」をもっと面白く、素敵なものにしていきたい。
それが、TEAMUSに込めた私たちの想いです。
------------------------------------------------------------------------------------------
*1:EDGAR H.SCHEIN ORGANIZATIONAL ORGANIZATIONAL CULTURE CULTURE AND LEADERSHIP
https://ia800805.us.archive.org/9/items/EdgarHScheinOrganizationalCultureAndLeadership/Edgar_H_Schein_Organizational_culture_and_leadership.pdf
*2:AWS Executive Insights: 「Powering Innovation and Speed with Amazon's Two-Pizza Teams」
https://aws.amazon.com/jp/executive-insights/content/amazon-two-pizza-team/?utm_source=chatgpt.com
*3:What is Your Organization’s Core Theory of Success?
https://thesystemsthinker.com/what-is-your-organizations-core-theory-of-success/

組織成長ソリューション
TEAMUSを
もっと知りたい方へ
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフがさらに詳しく
機能についてご説明いたします。