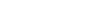強いビジネスチームとは何か? ~持続的成果を生む組織の設計図~
- 公開日:2025/7/24(木)
「強いチーム」と聞いて、どのような集団を思い浮かべるでしょうか。 売上目標を常に達成するエース営業部隊や、カリスマリーダーが率いる存在感ある集団などを想像されるかもしれません。 伝統的に、チームの「強さ」は売上や収益率、生産性といった比較的短期の定量指標、あるいはチームリーダーのプレゼンスなどの定性評価で測られてきました。 しかし、その見方は、チームが持つ真の力、特にその持続可能性を見過ごす危険性をはらんでいます。 本稿では、Google社が行った画期的な社内研究「プロジェクト・アリストテレス」を基点に、心理学や経営学の知見を統合し、「真に強いチーム」を構築するための本質的な要素を考察します。
目次
1. チームの礎となる「心理的安全性」

多くの企業が、「最高の成果は、最高の才能を集めることで生まれる」という信念のもと、採用と配置に莫大なリソースを投じています。Google社も例外ではありませんでした。同社は「プロジェクト・アリストテレス」と名付けた大規模な社内調査で、エンジニアから営業まで数百のチームを分析し、何がチームの生産性を決定づけるのかを解明しようと試みました。当初、メンバーの性格、学歴、趣味といった250以上の属性を分析しましたが、成果を予測する強力なパターンは見出せませんでした。
しかし、2年にわたる研究の末にたどり着いた結論は、従来の常識を覆すものでした。それは、「誰がチームにいるか」よりも、「メンバーがどのように相互作用し、仕事を構造化し、自らの貢献をどう捉えているか」が、はるかに重要であるという事実でした。この発見は、古代ギリシアの哲学者アリストテレスが「全体は部分の総和に勝る」と述べたように、チームの強さが個々の才能の総和ではなく相互作用の質から生まれることを科学的に証明したのです 。
つぎにプロジェクト・アリストテレスが突き止めた、チームの成功を左右する最も重要な因子、それが「心理的安全性」です。ハーバード・ビジネススクールのエイミー・エドモンドソン教授が提唱したこの概念は、「チーム内では対人関係におけるリスクを取っても安全であるという、メンバー間で共有された信念」と定義されます。具体的には、初歩的な質問をしたり、自らのミスを認めたり、斬新なアイデアを提案したりしても、誰もそれを理由に罰せられたり屈辱を与えられたりすることはないと確信できる状態を指します。
ここで重要なのは、心理的安全性をいわゆる「ぬるま湯組織」や「表面的な仲良しグループ」と混同してはならないということです。それは、常に快適で意見の対立がない状態を意味するのではありません。むしろ、互いへの尊敬を基盤として、建設的な意見の対立や率直なフィードバックを可能にするための土壌なのです。報復を恐れることなく本音で議論(ヘルシーファイト)できる環境こそが、真に心理的に安全な状態と言えます。
この心理的安全性が、ビジネスの成果に直結するドライバーであることは、Google社の調査が明確に示しています。心理的安全性の高いチームは、そうでないチームに比べて、離職率が低く、多様なアイデアを有効活用でき、収益性が高く、評価される機会が多いことが明らかになりました。
2. 心理的安全性の上に築く4つの柱

心理的安全性は最強の土台ですが、それだけでは十分ではありません。プロジェクト・アリストテレスは、その土台の上に築かれるべき4つの柱を示唆しました。これらの要素が全て揃い、相互に作用することで、チームは持続的な成果を生み出すのです。
-
信頼性 (Dependability)
各メンバーが、互いに期限内に質の高い仕事を仕上げてくれると信じられる状態。責任感への相互期待が、円滑な業務分担と複雑なプロジェクト推進を可能にします。
-
構造と明瞭さ (Structure & Clarity)
チームの目標、各メンバーの役割、そして目標達成までの計画が明確である状態。各人が自分に何が期待されているかを正確に理解していることが不可欠であり、これを実践する強力なフレームワークがOKR (Objectives and Key Results) です。野心的な目標(Objectives)と具体的な数値指標(Key Results)を設定し、会社、チーム、個人の目標を連動させることで、組織全体の方向性を統一し、各人の貢献を可視化します。 -
仕事の意味 (Meaning of Work)
メンバーが、自身の仕事に対して個人的な目的意識や意義を見出している状態。この「意味」は、経済的な安定から社会貢献まで人によって様々ですが、リーダーが日々の業務と組織のビジョンとの繋がりを示し、個々の動機を尊重することが重要になります。
-
仕事のインパクト (Impact of Work)
自分たちの仕事が重要であり、その成果が組織目標の達成に貢献していると実感できる状態。リーダーは、チームの仕事が顧客や社会に与える影響を定期的に共有し、この感覚を醸成する役割を担います。
これら4つの柱は、心理的安全性を土台として統合的に機能します。どれか一つが欠けても、チームは真の強さを発揮することはできません。
3. 「設計者・触媒」としてのリーダー

強いチームは本来自然には発生せず、意図的に設計され、育まれるものです。その過程において、中心的な役割を担うのがリーダーです。それゆえに現代のリーダーには、二つの顔が求められます。
-
環境を育むサーバントリーダーシップ
「リーダーはチームに奉仕するために存在する」という哲学に基づき、チームを底辺から支えるリーダーシップです。傾聴、共感、癒し、気づきといった行動を通じて、「自分は評価するためではなく、支援するためにここにいる」という強力なメッセージを発信し、チームにおける心理的安全性の基盤を築きます。
-
ミッションを鼓舞する変革型リーダーシップ
情熱的なビジョンを掲げ、メンバーの内面に働きかけるリーダーシップです。魅力的なビジョンで「動機付けの働きかけ」を行い、常識に疑問を投げかける「知的な刺激」を与え、一人ひとりに寄り添う「個別的配慮」を行うことで、「仕事の意味」と「インパクト」を醸成します。
リーダーは、チームの環境を整える「設計者(サーバントリーダー)」であると同時に、メンバーの潜在能力を最大限に引き出す「触媒(変革型リーダー)」でなければならないのです。
4. チームメンバーの役割認識と多様性

チームの役割理論で有名なメレディス・ベルビン博士が明らかにした「アポロシンドローム」の中で、知的に優れた人材ばかりを集めたチーム(アポロチーム)は、かえって凡庸な成果しか出せないことを指摘しています。これは、個人の能力の高さがチームの成功を必ずしも保証していないことを示しています。
ベルビン博士は、成功するチームには9つの異なる行動特性に基づく「チームロール(役割)」がバランス良く存在することも発見しました。チーム内の関係を円滑にする「人間志向」、アイデアを実行に移す「行動志向」、新しいアイデアを生み出す「思考志向」といった役割を担うメンバーが揃うことで、そのチームはあらゆる局面に対応できるようになります。
この役割のバランスという考え方は、多様性(ダイバーシティ)の重要性を示唆します。しかし、多様性は摩擦や対立を生む原因にもなり得ます。
ここで重要になるのが「包摂性(インクルージョン)」です。これは、多様なメンバー全員が尊重され、自分らしくいられると感じられる状態を指し、これも本質的には心理的安全性に近い概念です。つまり、心理的安全性というOSがあって初めて、多様な役割というアプリケーションはその真価を発揮するのです。
5. 困難・混乱を乗り越えた経験
心理学者ブルース・タックマンのチーム発達段階モデルは、チームが予測可能な段階を経て成長することを示しています。特に重要なのが、結成後の「混乱期(Storming)」です。この段階では、役割や目標を巡って意見の対立や衝突が発生します。
まさにこの「混乱期」こそが、チームが機能するか機能不全に陥るかの決定的な分岐点なのです。心理的安全性が低いチームでは、対立は個人的な非難に発展し、「衝突への恐怖」から機能不全の坂を転げ落ちます。一方、心理的安全性が高いチームでは、対立はアイデアを巡る「生産的な衝突」となり、相互理解を深め、より良い解決策を生み出す成長の糧となるのです。

最後に、ビジネスチームとしての強さを生むために
これまでの議論を統合すると、強いチームの構造が浮かび上がります。
それは、まず心理的安全性という強固な基盤の上に、信頼性、構造と明瞭さ、仕事の意味、インパクトという柱を築くことです。形成期のチームにこの土台をつくるのは、サーバントリーダーと変革型リーダーの側面を兼ね備えたリーダーに他なりません。
そのチーム環境の中でメンバーは互いに衝突をおそれずに影響し合いながら、多様な役割を認識し、それがチーム内にバランス良く配置されていきます。そして、チームが一丸となり、困難という嵐に立ち向かい、皆でそれを乗り越えた経験を共にする。
ビジネスチームの強さとは、静的な状態ではなく、まさに動的なプロセスなのです。それは、信頼を基盤とし、健全な対立を通じて学び、共通の目的に向かって互いを支え合う、生きたシステムそのものとも言えます。
強いチームを築く責任は、リーダーだけのものではありません。メンバー一人ひとりが、日々の行動を通じて心理的安全性を高め、互いへの信頼を寄せ、建設的な議論に参加することが、チームのカルチャーそのものを形作ります。そしてそのカルチャーが次のリーダーを生み、次の強いチームに繋ぐのです。
本稿が、貴社のチームを、持続的に高い成果を生み出し続ける「生きたシステム」へと変革させる一助となれば幸いです。

組織成長ソリューション
TEAMUSを
もっと知りたい方へ
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフがさらに詳しく
機能についてご説明いたします。