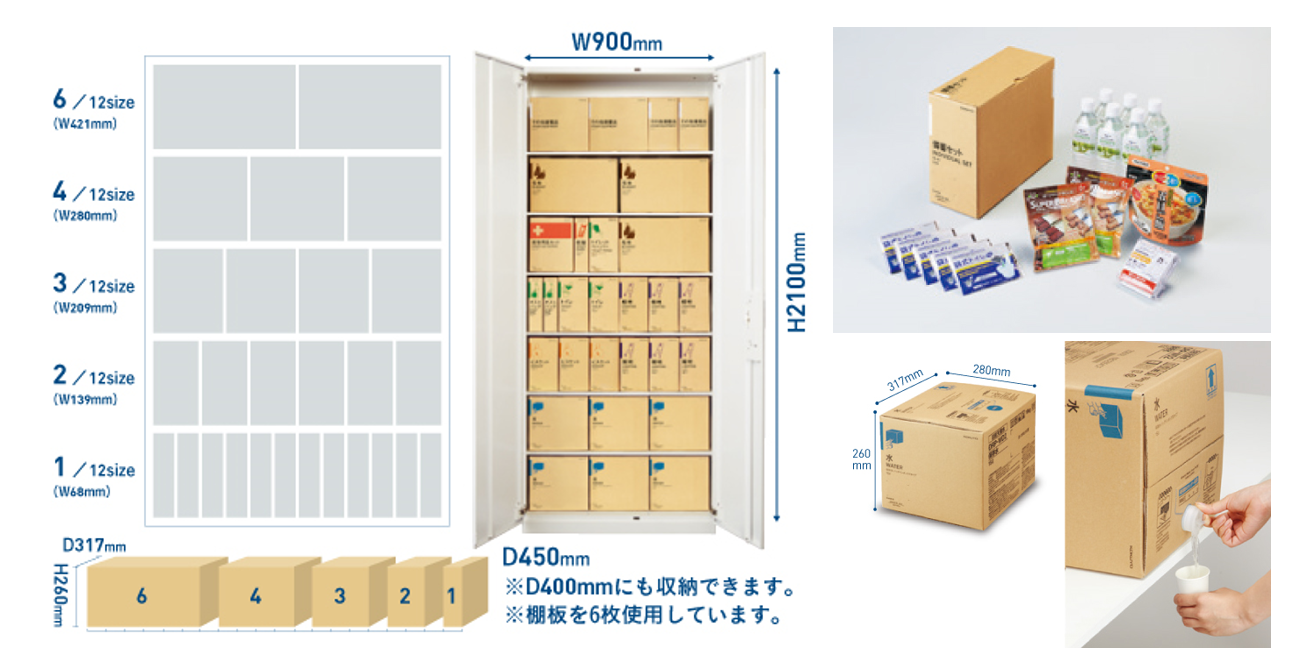HOME > オフィスづくりに役立つコラム > 働き方用語辞典「メンバーシップ型雇用」

メンバーシップ型雇用
業務内容を限定せずに雇用契約を結び、後から人材配置する日本独特の雇用システムのこと
「メンバーシップ型雇用」とは、職務内容や勤務地、勤務時間を決めずに採用し、人に合わせて仕事を割り当てる雇用形態のことです。多くの日本企業が取り入れていることから、日本型雇用とも呼ばれます。新卒一括採用を行い、ジョブローテーションを通して多様な知識やスキルを習得し、長期的に人材を育成するシステムです。年功序列・終身雇用を前提としており、異動や転勤などにより勤務環境が大きく変わる可能性があるのが特徴です。
■メンバーシップ型雇用のメリット
・柔軟な人材配置
業務内容や勤務地などが限定されていないため、会社の都合や欠員の補充の際に異動させることができる。
・採用コストの軽減
基本的に短期間に大勢の人材を採用するため、ジョブ型雇用に比べ採用にかかるコストを抑えることができる。
・長期的な人材育成
部署異動を繰り返すことで幅広い経験を積むことができ、時間をかけて計画的に人材を育成することができる。
・チームワークの強化
長期間勤務することで、社員同士の絆が深まり、チームワークの強化が期待できる。また、帰属意識(ワークエンゲージメント)が高まり、離職率の低下や定着率の向上につながる。
■メンバーシップ型雇用のデメリット
・スペシャリストの不足
配置転換により多様な業務を担当するため、特定の専門的な技術を持つ人材が不足してしまう。
・人件費の負担
年功序列に基づいているため、勤続年数の長い社員が多いほど人件費が増加し、会社にとって負担が大きくなる。
・生産性の低下
異動により興味のない職種や苦手な業務に配置されたり、成果を出したのに昇進や昇給の機会を与えられないなどを理由にモチベーションが下がり、生産性が低下する恐れがある。
海外では職務に応じて必要な能力や経験、資格を持つ人材を採用するジョブ型雇用が浸透しており、メンバーシップ型雇用とは対極にあるといえるでしょう。高い専門性が必要となるジョブ型雇用に対し、メンバーシップ型雇用は、人間性やポテンシャルが重視されます。近年は、働き方の多様化や業務の複雑化、少子化による人手不足などの時代の変化により、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へ移行する企業も増えてきています。
デジタル技術の進展に伴い、専門的で高度な技術や知識が求められる中、メンバーシップ型雇用を継続していくためには、社員のリスキリングが必要不可欠です。研修や教育を通して社員の成長を積極的にサポートすることで、企業の競争力を高めることができるでしょう。
連載コラム
 学べるコクヨの
学べるコクヨの
オウンドメディア
 コクヨ公式SNS
コクヨ公式SNS
働き方・家具・オフィス空間の
最新情報をチェック!