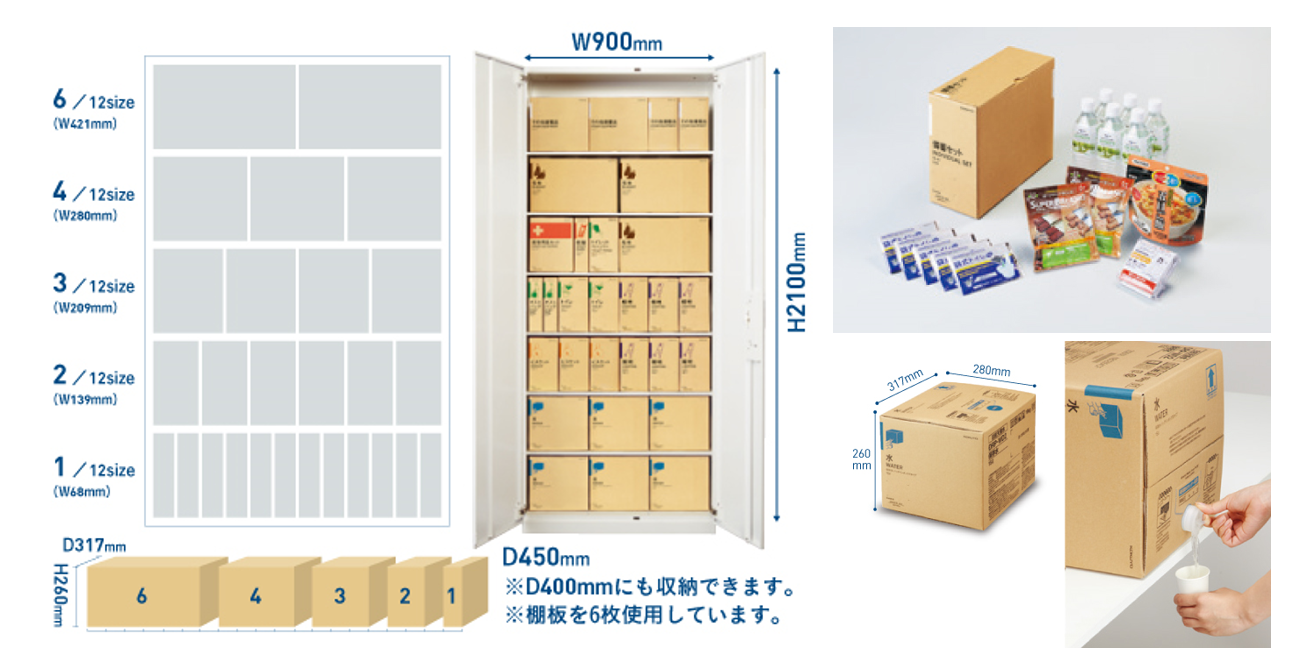HOME > オフィスづくりに役立つコラム > 働き方用語辞典「ジョブ型雇用」

ジョブ型雇用
職務に応じて必要な能力や経験、資格を持つ人材を採用する雇用方法
「ジョブ型雇用」とは、職務内容を明確に定義し、職務に適したスキルや経験、資格などの専門性を重視し採用する欧米で主流の雇用システムです。日本では業務内容や勤務地などを限定せずに採用するメンバーシップ型雇用が浸透していますが、近年、ジョブ型雇用を導入する企業が増加しています。
■ジョブ型雇用が注目される背景
・経団連の提言
経団連は2020年に「経営労働政策特別委員会報告」において、日本型雇用システム(メンバーシップ型雇用)の見直しとジョブ型雇用の推奨を提起。また、2022年の「春季労使交渉に臨む経営側の方針」では、ジョブ型雇用の導入・活用の検討が必要と発言された。
・テレワークの普及
コロナ禍によりテレワークが普及したことで、従来の人事評価制度では業務内容や成果の評価が難しくなり、ジョブ型雇用の導入を検討するようになった。
・終身雇用による人件費の負担
経済が停滞する中、長期雇用による人件費の高騰は企業にとって大きな負担となり、終身雇用制度の維持が難しくなった。
■ジョブ型雇用のメリット
―企業側
・即戦力となる人材確保
特定のスキルや業務内容を明確化して募集するため、即戦力となる最適な人材を確保しやすくなり、ミスマッチを防ぐことができる。
・正当な評価
あらかじめ職務内容や必要なスキルが定められていることで、上司の主観ではなく成果に応じた公平な評価ができる。
―求職者側
・スキルの向上
特定分野に特化した仕事に集中できるため、専門性が高まりスキルアップがしやすい。
・成果を収めやすい環境
得意分野の業務に取り組むため、成果を上げやすい。
・モチベーションの向上
成果やスキルを基準に評価されるため、モチベーションの向上が期待できる。
■ジョブ型雇用のデメリット
―企業側
・人材の流出 他社で好条件の求人があった場合、人材流出のリスクがある。
・配置転換の困難
他部署で人材が不足しても、会社都合での異動や転勤といった配置換えが難しい。
―求職者側
・自己研鑽への負担
高度な専門性を求められる場合、自主的に教育や研修などを通して技術を習得する必要がある。
・失職のリスク
景気や会社の都合、プロジェクトの終了などにより、業務や職務がなくなった場合、失職の可能性がある。
ジョブ型雇用の導入に向け、事前に明確な職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)を作成することで、ミスマッチやトラブルを防ぐことができます。職務内容や給与、スキル、経験、資格のほか、目標、責任・権限の範囲、評価基準など、具体的に定義するようにしましょう。また、キャリアの等級制度や報酬制度を導入することで、透明性のある公平な評価が可能になり、実績に応じた賃金の設定にも有効です。
連載コラム
 学べるコクヨの
学べるコクヨの
オウンドメディア
 コクヨ公式SNS
コクヨ公式SNS
働き方・家具・オフィス空間の
最新情報をチェック!